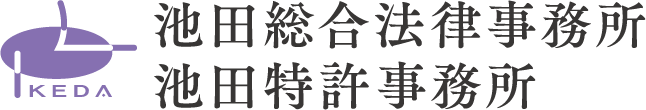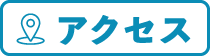相続・遺言・事業承継
相続
たとえば、父親がなくなり、残されたのが妻と子ども2人であれば、父親が遺言書を残さなければ妻と子供たちが父の遺産を相続する相続人になります。
この場合、父親の遺産を誰が引き継ぐかを妻と子供たちで話し合って決めることを遺産分割協議といいます。
しかし、人生で1、2回しかない遺産分割協議において、適切な遺産分割協議書を弁護士が関わることなく作成することは難しいことです。
また、遺産分割協議で合意ができなければ、家庭裁判所での遺産分割調停に進むことになりますが、その中で遺産の範囲やその金額の確定、特別受益の有無、寄与分の有無などの様々な法的問題を法的アドバイス無く検討し、ご自身で判断をしていくことも困難を伴います。
相続、遺産分割では、相続人の方々の様々な思いに加えて、複雑な法律問題も絡んできますので、どういった形での相続、遺産分割が最善かを検討し、判断していくには弁護士の関与が不可欠です。
遺言
遺言書は、自分が先祖から引き継いだり、自分で築き上げてきた財産を次の世代にどのように引き継ぐかの意思を明確にしておくものです。
自分の残した遺産のために、残された子どもたちなどが仲違いをし、他人のようになってしまうのは、誰も望んでいないことです。
残された人々の間で無用の争いが起きることを避けるためには、弁護士にご相談いただき、遺産の内容や相続人の状況を確認のうえ、可能な限り争いが生じない遺言書を残されることが重要です。
事業承継
事業承継とは、会社(事業)の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。いわば、事業の相続とも言える問題であり、実際上も、個人の相続との関連が強く見られます。
事業承継のパターンとしては、大きく「会社内部での承継」と「会社外部への承継」が考えられます。
前者においては、親族後継者へ承継する場合と従業員後継者へ承継する場合、の二通りが考えられます。また、後者の主たるものとしては、M&Aが挙げられます。
具体的な内容については、以下に記載をしていますが、いずれの方法をとるにしても、一朝一夕で対処が可能というものではありません。
そのため、まずは事業の現状把握をして対策の方向性を決め、早期の着手をすることが肝心です。
①親族後継者への承継
- 誰を後継者とするかということや、後継者の教育、そのための環境整備といった点は、当然に必要となってきます。
- 上記の点に加えて、後継者となる親族が、現経営者の相続人(子どもなど)である場合には、相続の問題が関連してきます。
- 特に、自社株式の譲渡の問題は、会社の経営権(議決権)と絡んでくるため、非常に重要です。経営を安定的に承継させるためには、後継者に自社株式も譲渡することが必要となります(少なくとも、三分の二以上の議決権を確保しておくべきです)。・・・後記参照
- 株式だけでなく、事業用の財産(不動産、動産)についても、相続によって散逸してしまい、会社経営に支障が出ることのないように注意する必要があります。経営者の個人所有から会社所有に変えるなどの対策も考えられます。
- 中小企業の場合には、金融機関に対して、オーナー経営者の個人保証がつけられていることが多いです。そのため、後継者もこのような個人保証を引き継ぐことは求められることが考えられます。
②従業員後継者への承継
- この場合も、誰を後継者とするかということや、後継者の教育、そのための環境整備といった点は、当然に必要となってきます。
- 経営者の個人保証の問題も、上記①の場合と同様です。
- 従業員(親族外)後継者への承継の場合には、自社株式の承継の点は、さらに問題となります。従業員後継者の場合、相続による株式の移転は出来ませんので、株式を買い取ることが一般的な方法となります。しかし、そのための資金的な余裕がない場合も多く、対応策が必要となってきます。
具体的な方法としては、種類株式の活用、MBO(マネジメント・バイアウト:経営陣買取)、などが考えられます。
③M&A(Mergers(合併)and Acquisitions(買収))
- 会社を他社に買い取ってもらうことで、事業内容を継続するという方法です。近年、中小企業におけるM&Aも増加傾向にあります。
- 適切な後継者が見つからない場合であっても、廃業ではなく、事業を継続し、従業員の雇用も確保できるという点で、有効な方法と言えます。
- ただし、譲渡先(買主)の会社が見つかるかどうかは、簡単な問題ではありませんので、時間的な余裕をもって検討を進めることが重要です。
税務面での問題
- 事業承継についても、資産の移転があれば贈与税や相続税が発生することになります。
また、非上場株式の譲渡所得に対しては、所得税及び住民税が課税されるということにも留意しなければなりません。 - さらに、中小企業の事業承継に特有の税制として、「事業承継税制」が存在します。この制度は、非上場株式の相続税及び贈与税の納税を猶予・免除するもので、相続だけでなく生前贈与による株式承継に伴う税負担を軽減することを目的とします。平成21年に導入された当初は、適用される要件が厳しく、なかなか利用件数が伸びないという状況になりましたが、平成25年改正(平成27年1月1日から施行)により、要件が緩和され、利用がしやすくなったと言えます。その後,平成30年改正により、さらに要件が緩和され、会社の全株式を適用対象にし、納税猶予割合も100パーセントに拡大されました。さらに、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象になるなど,使い勝手が良くなってきています。
- また、令和元年度税制改正で、青色申告をしている個人事業者のもつ事業用資産(特定事業用資産といいます。)の贈与、相続についても、同様の制度が導入されました(個人版事業承継税制)。
経営承継円滑化法の活用
- 事業承継における民法上の遺留分制度への対応や金融支援を目的とする法律として、平成20年5月に成立しました。
- その中でも、遺留分の特例は、事業承継に伴う自社株式の移転に関わる、重要な制度となっています。
- 遺留分の特例・・・相続が起こった場合、生前贈与や遺言によって後継者に自社株式を全て譲渡しようとしても、一定の法定相続人には、遺留分が認められます。
そのため、株式以外の財産によって遺留分を満たす遺産の分配が出来なければ、後継者相続人に対して、遺留分減殺請求がなされ、自社株式が散逸する危険があります。
また、生前に自社株式の贈与を受けた後継者が、その後会社の業績を向上させて株式の評価も上昇したという場合、原則としては、相続開始時の評価額で遺留分の算定がなされることになるため、後継者としては、増加した価値分も含め贈与を受けたと計算がされることになります。その結果、当初は予想していなかった遺留分侵害が生じる危険があります。
これらの事態に備えて、以下のような制度を民法の特例として設けています。
- ⑴生前贈与株式を遺留分の対象から除外できる制度(除外合意)
経産大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、自社株式等一定の財産を遺留分算定の基礎財産から除外することができます。 - ⑵生前贈与株式の評価を予め固定できる制度(固定合意)
経産大臣の確認を受けた後継者が、遺留分権利者全員との合意内容について家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分算定に際して、生前贈与された自社株式の価額を合意時の評価額で固定することができます。
いずれにしても、事業承継は、税務面、法律面で、難しい問題が控えており、弁護士、税理士、公認会計士等専門家等と共同して進めていくことが不可欠です。当事務所では、他の専門士業とも、提携関係にあり、連携して事業承継を円滑に進めていくことが可能です。事業承継をご検討の方は、是非、池田総合法律事務所にご相談下さい。
また、円滑化法の適用を受けるためには、具体的な経営見直し等を記載した「特例承継計画」(個人事業者の場合は「個人事業承継計画」)を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載する必要があります。当事務所には、認定支援機関の資格者が在籍しておりますので、ご安心してご相談いただけるものと思います。
-
Q1 被相続人の死亡から相当期間経過後に相続放棄はできますか?
生前ほとんど付き合いのなかった叔父が1年前に亡くなったのですが、最近になって、私が相続人であることがわかり、しかも叔父には借金があることがわかりました。今から相続放棄をすることはできるのでしょうか?
相続人となっていることがわかってから半年以上経って、叔父に借金があることがわかった場合はどうでしょうか?A1
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」「3か月以内」にしなければなりません。
この起算点については、「相続が開始したこと」及び「自己が相続人となったこと」を覚知した時というのが、裁判所の基本的な立場です。
そのため、自身が相続人となったことを知ってから3か月以内であれば、有効に相続放棄が出来るということになります。
ただし、被相続人に積極的な財産もなく、負債があることもわからないときには、相続放棄をしないでおくことも十分にありえます。
そのため、3か月以内に相続放棄をしなかったことが被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、そのように信じることに“相当な理由”があるときは、起算点は、「相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」からとなるとするのが、最高裁の立場です。よって、相談者の方の場合も、被相続人である叔父さんに相続財産があることを認識したか通常認識すべき時点から起算して3か月以内であれば、相続放棄をすることは可能ということになります。裁判所も3か月を経過した後の相続放棄でも、比較的柔軟に認める傾向にあります。
相続放棄でお困りの方は、池田総合法律事務所にご相談ください。 -
Q2 遺言の内容には従わないといけないですか?
父が遺言を残して亡くなりました。遺言の内容を見たところ、相続人である私と弟の希望とは異なる遺産の分け方が書かれていました。このような場合にも、遺言に従わないといけないのですか?A2
遺言は、亡くなった方が自身の財産をどう処分するかについての最後の意思ですので、可能な限り尊重することが望ましいです。
しかし、他方で、亡くなった方は残された相続人たちが相続で紛争にならないように、分割方法を指示することが通常で、相続人たちが納得のいく分割方法をとることを必ずしも否定する意図ではなかったと考えられます。
そのため、遺言が残されている場合でも、相続人全員の合意により、遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことは妨げられないのです。
遺言書や遺産分割協議でお困りの方は、池田総合法律事務所にご相談ください。 -
Q3 親の介護をし、家業も継いできたのですが、相続で考慮されますか?
私は、数年前に突然父が病に倒れたため、それから家業である古書店を切り盛りしてきました。また、父の介護も行ってきたのですが、何も手伝っていない弟たちよりも、多く父の遺産を相続する権利はありますか?A3
相続人の中に、身分関係上、通常期待される以上に「被相続人の財産の維持又は増加に、あるいはその扶養に、特別の寄与があった者」があるときは、相続分に加算して法定相続分による割合を修正することができます。これを「寄与分」と言います。相談者の方にも、この寄与分によって他の相続人よりも多くの遺産を相続することが考えられます。
遺産分割の協議をすると、この寄与分の主張がされることが多くあります(例えば、自分は親の面倒をよくみたから寄与分を認めるべきだ、など)。しかし、法律上「特別の」寄与であることが必要で、例えば扶養義務の範囲内の看護や介護では、寄与分は認められません。
寄与の類型は大きく、①家業が自営業者等で、被相続人の事業に従事していた場合、②一定の財産上の利益を被相続人に生じさせた場合、③被相続人の療養看護に従事した場合、④相続人が出費したために被相続人が出費を押さえられ財産の減少を免れた、あるいは財産が増加をした場合等があります。
寄与分が認められるためには、先に述べた「特別な」寄与であるためには、以下のような要件が、必要です。
⑴ 寄与が無償であることが必要です。ただし、家業に従事している場合等は、無償ではなくても、一般の賃金と比べて大幅に低額であれば、認められることがあります。⑵ 一定の継続性が必要です。「特別な」貢献という以上、相当期間の貢献が必要とされますが、何年以上という決まりがあるわけではありません。
⑶ 専従性、つまり、片手間ではなく、恒常的な負担を要するものであることが必要です。基本的に自分の仕事を持っていて、時々家業を手伝う、介護をするというような場合は、親族としての協力の範囲内と言うべきです。
さらに、特別の貢献によって、出費が押さえられて財産の減少を免れた、あるいは、増加をしたという関係(因果関係)が必要となります。
このような各要件を充足する場合には、寄与分が認められる可能性があります。ただし、裁判所での認定を得るためには、当事者の主張のみでは足りず、客観的な資料による立証が必要となってきますので、この点にも注意が必要です。
相談者の方の場合、家業に従事した点は、別に従業員を雇うよりも相当安い給料で働いたことや従前の勤務先を辞めて家業に専念したこと、などの事情が必要となってきます。また、介護に関しては、施設入居が相当な状態を在宅介護でケアしたというような事情が必要となってきます。
寄与分の主張・立証には、弁護士としてアドバイスさせていただける点が多数ありえます。
遺産分割協議、寄与分などでお困りの方は、池田総合法律事務所にご相談ください。 -
Q4 相続人から外したい人がいるのですが、どうしたらいいですか?
私には、3人の息子がおりますが、長男は昔から私に迷惑ばかりかけてきて、今も性格が合わず疎遠な状態です。長男には、私の財産を相続させたくないのですが、相続人から外す方法はありますか?A4
相続させたくない人がいる場合、遺言でその人に何も財産を残さない内容の記載をすることはあり得ますが、遺留分(遺言でも侵害できない権利)を持つ妻や子などの場合には、全ての権利を奪うことはできません。
そこで、被相続人が主体的に行うことができる行為として、相続人の「廃除」という制度があります。これは、生前ないし死後に(死後の場合は、遺言に記載しておきます)裁判所へ申立てを行って、裁判所の審判または調停によって決定されるものです。
裁判所によって廃除が認められるためには、①相続人が被相続人に虐待をしたこと、②相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと、③相続人にその他著しい非行があったこと、のいずれかの理由がなければいけません。相続人の権利を一方的に奪う強力な制度のため、その要件は厳しいものとなっていますし、その事実を客観的に認定する必要があります。相談者の方の場合には、性格が合わないという程度の事情ですので、廃除の要件に当てはまると考えることは困難です。しかし、例えば、遊興費を得るために多額の借金をし、その返済を肩代わりさせたなど、重大な事由があれば上記③に該当することはあり得ます。また、親子喧嘩で一時の感情によって侮辱的な言葉を言ったという程度では、上記②には該当しないとされています。
なお、遺言によって廃除の意思表示をする場合には、虐待等を受けた本人である相続人が存在しないため、要件に当てはまる事情の証明を行うことが困難なことも少なくありません。そのため、生前の申立てによることが望ましいと思われます。
相続の内容についてご検討の方、廃除も検討したい方は、一度、池田総合法律事務所にご相談ください。 -
Q5 高価な美術品がありますが、相続税が払えません。どうしたらいいですか?
父が亡くなり、私が相続人の一人となりました。父は生前美術品収集を趣味にしており、常々、総額ではかなりの金額のコレクションになると言っていました。父には他にも不動産や預貯金等の財産があり、美術品の金額によっては相続税を支払えない可能性が出てきます。相続人は皆、美術品に興味がなく、管理も十分に出来ないのですが、なにかいい方法はありませんか?A5
亡くなった方(被相続人)の所有していた財産であれば、美術品についても当然遺産として相続税計算の基礎となります。
美術品や骨董品の相続税計算上の評価は、国税庁の通達によると、「精通者意見価格等を参酌して評価する」すなわち専門家の鑑定によるものとされています。そのため、まずは鑑定をしてみないと評価がわからないということになってしまいます。被相続人の言葉では価値のあるものということでも、実際には違うこともあり得ます。
ただし、それほど価値のないものにまでわざわざ鑑定をしてみなければいけないとなると、鑑定代も相当かかります。そのため、購入価格数十万円程度のものは、「家財」として処理することが可能とされています。鑑定をした結果とても高価な美術品であった場合、その評価額が相続税算定の基礎となってしまいますので、当然高額の相続税が課されることになります。そうすると、相続税を支払うことも簡単ではありません。
特に、美術品を手元に残すことにこだわりがなければ、売却してしまうことも一つですが、売却に伴う課税関係の問題がありますし、即座に処分できるかどうかも不明確です。そこで一つ考えられるのが、美術品を寄付するということです。
相続税の申告期限までに、取得した財産を国・地方公共団体・公益事業者(社会福祉法人や学校法人など公益を目的とする法人)に贈与(寄付)すれば、その財産については相続税の課税価格に含まれないことになるという特例があるのです。贈与をした後は、相続税の申告書に、この特例の適用を受けることを記載し、贈与した財産の内容の明細書、贈与の相手方の証明書を添付すればよいというわけです。
池田総合法律事務所では、税理士とも協力しながら、より良いご提案をさせていただくことも可能です。
一度、池田総合法律事務所にご相談ください。