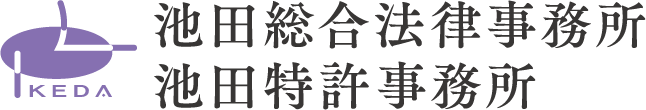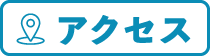「相続させる」遺言と遺贈
推定相続人に何かの遺産を残したいというときは、「~に相続させる」という遺言の文言により、物件等の特定に問題がなければ、その遺言に基づいて(但し、自筆証書の場合は、裁判所の検認手続を経て、検認済の証明が遺言書自体に添付されていることが必要です。)、取得した人が、単独で相続登記や預貯金の解約等をすることができます。

推定相続人でない人に、何かを「相続」してもらいたいとき、たとえば、子どもではなく、孫にやりたいといった場合には、相続人ではないので、遺贈をするということになります(この場合は、厳密には「相続」ではないので、「相続させる」ではなく「遺贈する」との記載が適切です。)。遺贈は、贈与契約ですので、名義変更、解約の手続のためには、相続人の実印、印鑑証明書が必要となってきます。したがって、相続人が多数いる場合や、相続人の協力が見込まれないときは、あわせて、遺言で遺言執行者を指定しておく方が簡便です(遺言で指定がなくても、相続開始後に裁判所に申立てをして、選任してもらうことも可能です。)。
また、遺贈の仕方は、特定遺贈と包括遺贈があり、個々の物件を特定して遺贈するものが前者、そうではなく、相続財産をすべて遺贈するとか、一定の割合で遺贈するといった場合が、包括遺贈となります。
包括遺贈の場合は、相続人とみなされて(民法990条)、債務もその割合に応じて負担をすることになり、遺贈の放棄も可能ですが、一部だけ遺贈を受けて、残りを放棄するということは出来ません。この点は大切な点です。
また、農地の譲渡等、農地法上の許可についても、包括遺贈の場合は不要ですが、特定遺贈の場合は必要となります。
相続人以外の方に「相続」してもらうためには、遺言の内容をどのようにするか、慎重に対応する必要があります。弁護士等の専門家のアドバイスをうけながら、進めていかれることをお勧めします。(池田伸之)