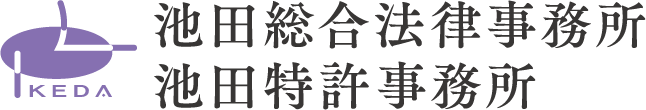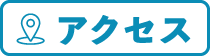オンライン(リモート方式)で公正証書遺言が作成できるようになりました
遺言書には、自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成してもらう公正証書遺言があります。それぞれメリット・デメリットがありますが、①法律上の要件を満たさず無効になるという心配がほぼない、②紛失の心配がない、③遺言者死亡後の手続きが簡易、などの理由により、多くのケースでは公正証書遺言を作成することをお勧めしています。
公正証書遺言を作成するには、一般的に公証役場に出向いて作成をしてもらいます。入院中であるなど、何らかの理由で公証人に来てもらって作成することも可能ですが、出張料金などがかかります。
そんな中、2023年の公証人法改正により、今年(2025年)10月1日以降に公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録で作成されることとなりました(改正公証人法36条:公正証書のデジタル化)。公正証書は、従前は紙で作成されていましたが、今後はPDF形式の電磁的記録で作成され、そこに電子サインや電子署名が付されたものが原本となります。
公正証書のデジタル化に伴い、公正証書の作成にあたっても、①公正証書作成の依頼者(嘱託人)の申し出があり、②他の嘱託人に異議がなく、③公証人が相当と認めた場合には、公証役場に行かなくても、ウェブ会議により公証人や他の列席者と相互の状況を確認する方法(リモート方式)で公正証書を作成できるようになりました(改正公証人法31条)。
※リモート方式で作成できるのは、上記①~③の要件を満たすときですので、そもそもリモート方式を希望しない場合には、従前通り、公証人と対面で作成します。
具体的な手続きは以下の通りです。
⑴ リモート方式に必要な機器等
まず、ウェブ会議に参加するための機材として、①パソコンと②カメラ、マイク、スピーカーが必要です。タブレット型PCやスマートフォンなどは、「電子サインを行う際に、公証人や他の列席者が、画面上の電子サインの状況と電子サインを行っている列席者の様子を同時に確認することができないため」、不可とされています(日本公証人連合会ウェブサイト 公正証書( https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01 )Q8)。
また、公正証書のPDF原本に電子サインをする必要があるため、③タッチ入力が可能なディスプレイ又はペンタブレット及びタッチペンが必要になります。
さらには、手続きを進めるため、④ウェブ会議中に使用するパソコンで送受信可能なメールアドレスが必要になります。
⑵ リモート方式の申し込み
リモート方式の申し込みにあたっては、まず、公証人に事前相談をすることになります。公証人が事前相談の結果、リモート方式が相当であると判断した場合には、ウェブ会議利用申出書を提出します。
リモート方式を利用する場合には、本人確認資料として、印鑑登録証明書又は署名用電子証明書の提出が必要です。
ウェブ会議への参加は、ウェブ会議利用申込書に記載したメールアドレスに送付されるウェブ会議の招待メールから参加します。
公正証書を電磁的記録として作成できるようになる日は、公証人によって異なります(改正公証人法7条の2参照)。東京の公証人から順次可能になる予定です。
日本公証人連合会ウェブサイト:
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/20250929.html
リモート方式を利用すれば、公証役場に出向くことが困難な場合でも、以前より気軽に公正証書遺言が作成できるようになります。もっとも、リモート方式を利用したいが、パソコンなどの扱いになれておらず、心配に思われる方もいらっしゃると思います。
その場合には、弁護士のような専門家が、遺言書の内容から作成に至るまで、お手伝いをさせていただくことが可能です。
遺言書の作成についてお悩みの方は、池田総合法律事務所にご相談ください。
(川瀬 裕久)