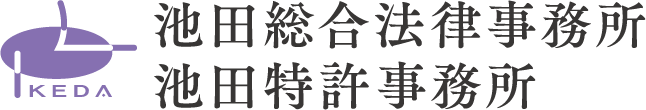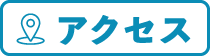下請法改正(2)
前回の下請法改正(1)に引き続き,製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)の概要を解説します。
1 運送委託の対象取引への追加
前回の下請法改正(1)でもふれましたが(リンクはる),発荷主と元請運送事業者との関係にも取適法が適用されることになります。
これまでは,製造,修理,情報成果物の作成,役務(サービス)提供の委託取引に下請法の規制は限定されていました。この役務提供の委託取引は,「再委託」を指していたので,運送業者が別の運送業者に運送というサービスを再委託した場合には,下請法の規制が及んでいました。
他方,メーカーや卸売事業者等が,荷主として,自社で製造した製品や自社で販売する商品の顧客向けの運送を運送業者に委託したとしても,「再委託」ではなく,下請法の規制が及ばないので,メーカーや卸売事業者等と,その物流を担う運送業者との間には独占禁止法以外の規制がありませんでした。
しかし,メディアなどでも取り上げられているように,メーカーや卸売事業者等の発荷主が運送業者に対して,無償で荷役をさせたり,指定された日時に物品を納入することを求めた結果等で荷待ちを求められたりという問題が顕在化してきました。
そのため,取適法2条5項で新たに「特定運送委託」という取引が定められ,発荷主と運送業者との間にも,取適法の規制が及ぶようになります。
そこで,発荷主としては,取適法の規制対象となる運送業者との取引の洗い出しを行ったうえで,取適法4条が定める代金の額,サービスの内容,支払期日・支払方法その他の事項が明示された書面を中小受託事業者に対して交付するように運用を修正する必要があります。加えて,取適法3条が定める運送サービスの提供を受けた日から60日の代金支払も遵守する必要があります。
また,運送業者としては,取適法の規制する特定運送委託に該当するかを,個々の荷主毎に検討し,燃料費や人件費の高騰での運送事業の採算悪化を改善できるよう,荷主側と交渉するきっかけにできれば,事業継続がし易くなると思われます。
2 従業員基準の追加
下請法では,下請法の規制対象となる場合を資本金を基準として定めていました。
しかし,事業規模に比べて資本金が少額である事業者には下請法の規制が及ばず,さらには減資をすることで下請法の規制を免れる事例や,そもそも受注者側に増資を求めて規制を免れようとする事例もあったとのことです。
そこで,取適法では,従業員数の基準が新設されます。
具体的には,
①製造委託,修理委託,情報成果物作成委託(プログラムの作成に限定),役務提供委託(運送,物品の倉庫保管,情報処理に関するものに限定),特定運送委託
「従業員300人超」の事業者が,「従業員300名以下(個人も含む)」に製造委託する場合
②①以外の情報成果物作成委託・役務提供委託
「従業員100名超」の事業者が,「従業員100名以下(個人も含む)」に情報
成果物作成委託,役務提供委託をする場合
が従業員数の基準となります。
そこで,取適法の規制が始まる前に,取引先の従業員数も確認しておき,規制に備えておく必要があります。
3 最後に
今回の改正により、取適法の規制が始まる前に事業者として準備する必要がある事項があります。
今回の改正では,事業を所管する事業所管省庁にも指導・助言権限が付与されることになりますので,コンプライアンスの観点からも,取適法の内容を正確に把握し,事業が法規制に合致しているのかを整理していく必要があります。
事業をするうえでコンプライアンスに関するアドバイスは,池田総合法律事務所でも多数の事業者様に提供している主要なサービスの1つです。御社の対応は万全ですか。是非、一度,当総合法律事務所にご相談ください。
(小澤尚記(こざわなおき))