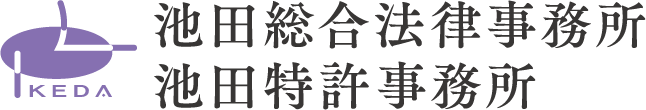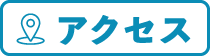交通事故と刑事手続 ~危険運転致死傷罪その他~
1 交通事故における刑事手続
交通事故の中でも,事故の相手が死亡する,怪我をするという人身被害(人身損害)が生じた人身事故の場合は,刑事手続の問題も出てきます。
なお,物損事故の場合は,当て逃げの場合は道路交通法違反(道路交通法72条(交通事故の場合の措置)の規定違反についての117条及び119条),で刑事手続になる可能性はありますが,本コラムでは省略します。
では,人身事故の場合に適用される可能性のある刑罰を順にご説明します。
2 過失運転致死傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号。自動車運転処罰法)第5条は,「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。」としており,これが過失運転致死傷罪になります。
この過失運転致死傷罪は,「自動車の運転上必要な注意を怠った」,つまり過失(≒ミス)によって,人が死傷した場合を処罰するものですので,自動車を運転する上でのミスが問題になるものです。そして,ほとんどの交通事故は自動車の運転上のミスによるものですので,この過失運転致死傷罪が適用される刑罰になることは多くなります。
なお,刑の免除(免除も有罪判決の一種ですが,判決で刑の言い渡しをしない,というものです)が定められていますが,実際に刑の免除をされたのは,
①東京高等裁判所平成17年5月25日判決
いずれも中学生の被害者のうち1名が加療約3日間を要する腰部挫傷,もう1名が加療約2週間を要する腰部挫傷,右股関節捻挫の事案で,いずれも傷害が軽いこと,保険から既に十分な損害賠償がなされていること,運転者が被害者2名に怪我をさせたことについて確かな認識があったのに現場から立ち去ったとまでは認められないとして,免除をした
②横浜地方裁判所平成28年4月12日判決
信号のある交差点で一時停止した後,信号にしたがって左折中に,横断歩道を移動中の自転車に気づかず,自転車に衝突し,被害者に加療約1週間の頸椎捻挫等の怪我をさせた事案で,運転者が当初から事実をほど認め,被害者に謝罪していたこと,一度不起訴処分となったものを起訴したものであるといった事情を考慮して免除した
というものがあります。しかし,いずれも特別な事情があるものですので,免除の判決は例外的なものにすぎません。
3 危険運転致死傷罪
(1)危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条のもの)の概要
自動車運転処罰法第2条は,アルコール等の影響により正常な運転が痕案な状態で自動車を走行させる行為などの行為をし,人を負傷させた者は,15年以下の拘禁刑に処し,人を死亡させた者は1年以上の有期拘禁刑に処する,としています。
具体的には,
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の直前に進入し,その他通行中の人又は車に著しく接近し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤車の通行を妨害する目的で,走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
⑥高速自動車国道(・・中略・・)又は自動車専用道路(・・中略・・)において,自動車の通行を妨害する目的で,走行中の自動車の前方で停止し,その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより,走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑧通行禁止道路(・・中略・・)を進行し,かつ,重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
の8個の類型が定められています。
この危険運転致死傷罪は,故意犯(8個の類型の運転をする故意や,8個の類型の運転にあたる可能性があることが分かっていながら運転をした未必の故意の場合)ですので,過失を前提とする過失運転致死傷罪とは全く違う刑罰です。
(2)危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法3条のもの)の概要
自動車運転処罰法3条は,2条とは別に,「アルコール又は薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で,自動車を運転し,よって,そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り,人を負傷させた者は12年以下の拘禁刑に処し,人を死亡させた者は15年以下の拘禁刑に処する」(3条1項)と定めています。
2条と違って3条は,走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転することが犯罪に該当するとしている点が異なります。
(3)危険運転致死傷罪の判断の難しさ
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難
危険運転致死傷罪のアルコールの影響は,道路交通法の酒酔い運転(道路交通法117条の2第1項)の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」とは概念が異なります。危険運転致死傷罪では,ハンドル,ブレーキ等を適切に操作したり,前方を注視したりすることが現に困難な状態であることが必要になります。
そうすると,人によって,飲酒のスピード,量,体調等で,同じアルコールの摂取量であっても,ハンドル,ブレーキを適切に操作できる場合もあれば,できない場合もあるのではないかという問題があります。
②進行を制御することが困難な高速度
的確な運転操作を行うことが困難になるほどの高速度である必要があります。
しかし,路面状況,車の車種やその状態,荷物の積載状況といった様々な要因で,的確な運転操作を行うことが困難な高速度か否かが変わることになります。アスファルト舗装されているか、砂利道か,雨が降っているか,アイスバーンか,車のタイヤがノーマルタイヤかスタッドレスタイヤか,過積載かといった様々な要因で,どの程度の速度で,的確な運転操作が困難になるかは違ってきます。
法定速度の何倍といった形で定められていないので,これも適用するにあたって検討すべき事情が多数あります。
③進行を制御する技能を有しないで走行
ハンドル,ブレーキ等の基本的な運転装置を操作する初歩的な技能も持っていないのに自動車を走行させる場合になります。
しかし,無免許運転であっても,基本的な運転操作ができるのであれば,進行を制御する技能を有しないで走行したことには該当せず,危険運転致死傷罪は成立しません。
④著しく接近
著しく接近は,例にすぎませんので,幅寄せすること,煽ること等も含まれる概念です。
⑤重大な交通の危険を生じさせる速度
重大な交通の危険を生じさせる速度は,自車が相手方に衝突すれば大きな事故を生じさせると一般に認められる速度,相手方の動作についていくなどして大きな事故になることを回避することが困難であると一般に認められる速度のことを言い,高速度であることは求められていません。
しかし,何をもって大きな事故を生じさせると一般に認められる速度かは明確に定められていませんので,この適用には難しさがあります。
(4)法制審議会-刑事法(危険運転による死傷事犯関係)部会の議論状況
以上のように,危険運転致死傷罪は抽象的な概念が多数入っており,危険運転致死傷罪が適用されるかどうかの判断には難しさがあります。
そこで,法改正が検討されており,現在の法制審議会では,血中アルコール濃度を法律上明記したり,道路の最高速度と「困難な高速度」との関係を明確に定めることができるかなどが議論されています。
4 まとめ
危険運転致死傷罪で逮捕勾留された場合であっても,本当に危険運転致死傷罪が適用できる事案かを分析し,捜査機関側とどのように対峙していくかを検討する必要があります。また,もし起訴されたとしても刑事裁判でどのように対応していくかも慎重な検討を要します。
池田総合法律事務所では,交通事故による刑事事件も含む刑事事件を取り扱っていますので,刑事事件でお困りの方は,池田総合法律事務所に一度ご相談ください。
〈小澤尚記(こざわなおき)〉