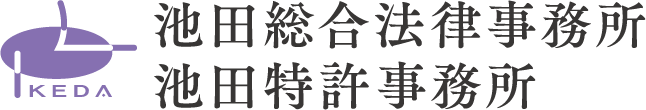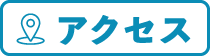患者が「説明された」「同意した」と納得できるインフォームドコンセント
1.はじめに
インフォームドコンセントが、医療に当たって重要なものであることは、医療にかかわる人のみならず、患者・家族側にも浸透して来ていることは、争いのないところです。しかし、医師や医療機関の側では、未だ、とにかく同意書を取っておけば、後で裁判になっても大丈夫、といった感覚でいる人も少なくありません。そのような発想から、エセ・インフォームドコンセントとでも言うべき、極端に防衛的な運用に接することもまだまだ少なくありません。
また、患者側から見ますと、説明を必要とするのは、重要な手術といった典型的な場面だけではありません。診療過程で生じる様々な場面での説明を求めても叶えられていない実情があります。そこでは医療者にとって、患者はコミュニケーションする相手ではなく、単に「診療の対象」の域を出ていないとも言えます。患者側は不満を募らせているという場面も少なからず見受けられます。
次々とやってくる患者に対応するのが精一杯で、とても個々に充実したインフォームドコンセントのプロセスを経る事など時間的には出来ないし、理想論だという声があることは承知のうえで、敢えて申し上げますが、こうした状況は長い目で見た場合、「客離れ」も生じ、医療機関の経営上もマイナスに作用するものです。医療機関としては、インフォームドコンセントの問題は医療を構成する重要な要素である、医療行為の中にインフォームドコンセントの過程がビルドインされているものである、というぐらいに考えていただきたいことを強調しておきたいと思います。では、医療者側と患者側との真のインフォームドコンセントを含めた診療関係を取り結ぶためには、どのようなことが必要とされるか、考えて見たいと思います。
2.「説明」「同意」の医療における位置づけ
医療行為は、その本質において、患者の体に対する侵襲となり、たとえば、手術は外形的には、刑法上の「傷害罪」を構成します。その違法性を阻却する(違法性を払拭する)1つの要素として、患者の「同意」が位置付けられています。いくら医学的に適応があり、医療水準を満たし、医療的に見て正当な行為でもあっても、患者の意思に反して行われる医療行為は専断的な医療行為として違法性を免れません。
これに関連して、有名な事件として、エホバの証人事件を紹介します。宗教上の理由からいかなる場合にも輸血を拒否するという固い信念を持った患者に対して、肝臓の腫瘍摘出手術をする場合に救命手段として輸血しかない場合もありうることの説明もせず、手術中に輸血をしたことに対し、手術を受けるかどうかの患者の意思決定の権利を奪ったものとして、人格権の侵害ありとした事例です(最判 平成12年2月29日)。信仰を背景とした輸血拒否事案という特殊な例ではありますが、患者自身の意思決定が、生命・身体に勝るとも劣らない重要な人権の一つであることを明らかにし、医療行為に当たって、「同意」の比重が如何に重いかを示す裁判例です。
改めていうまでの事でもありませんが、手術等の医療行為にあたっては、緊急の場合等はともかくも、原則として、必要な情報が予め医師から説明され、患者がその説明内容を十分に理解したうえ、同意されたものであることが必要です(医療法1条の4第2項では、医療を提供するにあたっては、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない、とされています。)。また、「説明」は診療契約に基づく義務として構成されるのが一般的で、「同意」という患者の自己決定の権利を保障するためのものです。
「説明書」はこの説明を補うためのものであり、「同意書」は患者がその説明に納得して「同意」したことの証拠となりうるものですが、「説明書」「同意書」がインフォームドコンセントの全てではなく、必要なプロセスの一部を構成するにすぎません。したがって、説明書を渡し、同意書に署名・押印があれば、それで直ちに免責されるものでもありません。
また、インフォームドコンセントは、医療と患者との間のコミュニケーションの結果生まれるもので、医療者側が「伝えた」つもりの情報や説明が、患者側に必ずしも「伝わる」わけではなく、患者側に伝わってはじめて有効な「同意」がなされた、といえるわけです。
したがって、たとえば患者の理解を超えた難解な説明書をただ渡しただけでは、「説明」をしたことにはなりませんし、患者に応じ、患者の理解力に応じた説明方法を工夫しなければなりません。最近は随分とわかりやすい説明書が増えてきた印象はありますが、それで事足るわけではなく、患者の理解力に応じた説明が個別に求められます。
患者の理解力に問題がある場合や、重大な手術等の前には、患者だけでなく、家族にも立ち会いを求めて時間を取って、画像などを見ながら、説明をすると言うことも普及してきており、こうした「伝わる」ことへの不断の努力が必要です。
3.「患者が納得出来ない説明」について考える
医療訴訟においては、患者側から医療者側の説明義務違反が主張されるケースが非常に多いのが、実情です。訴訟にあたっては、通常、診療プロセス(検査、診断、治療等)上の過誤を捉えて、注意義務違反を構成して、主張しますが、その主張が認められない場合に備えて、患者側では予備的に(第2次的に)説明義務違反の主張をしておくという、訴訟戦術的な一面もあることは否定できません。しかし、それにとどまらず、やはり、医療において医師等の説明義務が社会的に見ても幅広く重要なものとして、位置付けられてきていることの証拠ではないかと思われます。
また、患者サイドから見た場合、こうした説明義務違反(その大半は説明不足)が、訴訟提起に大きくドライブをかける原因になっているのかもしれません。
不十分な説明が問題となった、裁判例を紹介します。
産科例で、帝王切開か、経膣分娩かの選択に関する説明義務が問題となった例です。骨盤位(逆子)であることから、帝王切開術による分娩を強く希望していた夫婦に対し、担当医の説明により経膣分娩を受け入れたところ、分娩後間もなく子が死亡したという事例です。担当医は一般的な経膣分娩の危険性について一応の説明はしたものの、問題となっている胎児の最新の状態とそれとの関連で経膣分娩を選択する理由については、十分に説明をしなかった上、分娩中に何か起こったらすぐに帝王切開に切り替えられるから心配ないと誤解を与える説明(判決文によれば、実際には破水後に帝王切開に移行しても胎児の娩出までには少なくとも15分程度の時間を要し、経膣分娩よりも予後が悪いという事態がありえ、実際そのような経過をたどり、骨盤位牽引術により分娩に至っています。)をしたものとして、説明義務を尽くしたと言うことは出来ない、としました(最判平成17年9月8日)。
ではどこまでの説明が必要とされるのでしょうか。判決文をそのまま引用してみますと、
「分娩誘発を開始するまでの間、胎児の出来るだけ新しい推定体重、胎位、その他の骨盤位の場合における分娩方法の選択に当たっての重要な判断要素となる事項を挙げて経膣分娩によるとの方針が相当であるとする理由について具体的に説明するとともに、帝王切開は手術までに一定の時間を要するから、移行することが相当でないと判断される緊急の事態も生じ得ることなどを告げ、その後、陣痛促進剤の点滴投与を始めるまでには、胎児が複殿位であることも告げて、胎児の最新の状態を認識し、経膣分娩の場合の危険性を具体的に理解した上で、(当該)医師のもとで、経膣分娩を受け入れるか否かについて判断する機会を与えるべき義務があった」としています。
最近では、医療情報もネットなどを通じて、容易、かつ、かなりの精度で患者側が情報を入手出来るようになり、複数の治療方法がある場合に、患者側が特定の治療方法について、強い希望を持つような事は、今後も益々増えてくるでしょう。こうした場合に、患者側の希望する方法を取らず、異なった選択をしてもらうに当たっては、より丁寧かつ誤解を与えない説明が求められることになります。
4.「患者が納得出来る説明」に当たって、医療現場で望まれること-その具体的な方法について
まず、前述したように、「伝える」ことと「伝わる」ことは全く別問題で、そのことを医療者は自覚して、説明に当たる必要があります。インフォームドコンセントは、コミュニケーションの場で形成されるもので、その為には「患者に話すのではなく、患者と話すこと」(talk with,not to patents.(クリフトン・K・ミーダーDr.『ドクターズルール425』(医師の心得)276、南江堂、福井次夫訳)に留意して患者と接する心構えが必要です。
具体的には、次のようなことがインフォームドコンセントにあたって望まれます。
(1)緊急の場合はともかくも、説明は余裕をもった日時をおき、また、説明をする日と同意をもらう日の間には間隔を置くべきで、即日、その場で同意をするようなことはすべきではありません。
インフォームドコンセントは説明を受けた上で、治療を拒否することも含まれており、切迫した段階での説明やその場で同意を求めることは、こうした権利行使の機会を奪う事になります。
(2)説明の内容としては、医療行為の名称、内容、それによって期待される結果は勿論のこと、代替治療の有無、内容、副作用や合併症の内容や頻度、予後や患者負担の費用等が含まれているものであることが望ましいものでしょう。
合併症や副作用をどこまで伝えるかは、悩ましいところですが、頻度の高い者は説明すべきですし、頻度が低くても、予後に重篤な影響を与えるものはしっかりと説明すべきでしょう。
(3)「先生に全てお任せします」という患者に対して、説明、同意書は書いてもらったとしても有効な説明、同意とはなりません。こうした患者に対しても、工夫をして、ちゃんと「説明」をして「納得」してもらう努力をするべきです。
(4)説明書、同意書は、患者から「取る」ものではなく、共有すべきです。説明書や同意書の副本(コピー)を患者に渡さない医療機関がまだまだ見受けられます。定型的な説明文書のみならず、個別の患者ごとに作成される説明図も含め、コピーを交付するべきです。
(5)理解してもらっていない患者に対しては、一回の説明にとどまらず、複数回試みたり、または、家族の立ち会いを求めたり、違う場面での説明を試みたり、看護師に行ってもらうなど、理解のための工夫をするべきです。
(6)理解を求めるために専門用語を使用しない説明資料や図面、イラスト等を工夫し、たえず改訂していく努力が必要です。その内容の検討に当たっては、医療者だけでなく、患者の意見も聞き、改善に向けての方策がとられていることが望ましいと考えられます。そこまでは、難しいとしても、少なくとも各診療科ごとの医療者のみの関与ではなく、医療行為に直接携わらない、たとえば事務部門の人達の意見も取り入れて、わかりやすい説明資料の作成を心がけるべきです。
(7)上記3で挙げた裁判例にあるように、説明書面等により、一般的な説明に終始するだけでは不十分で、個々の患者の病態に応じた個別具体的な説明を心がけることが必要です。
(8)いまだに、同意文言のほかに、「一切の事故の責任は問わない」といった異議放棄文言が入った同意書を見かけますが、こうした事前の一般的な免責文言は、法律的には意味はありません。医師と患者の関係に対する医療機関の意識の低さ、無理解を自認しているようなものですので、早急に削除の方向で見直されるべきと考えます。
5.医療事故調査制度と「説明」
本年10月1日より施行されることになった医療事故調査制度では、報告、調査義務の対象となる医療事故については、医療行為に起因した死亡等で、医療機関の管理者が予期しなかったものが対象となります。
この「予期しなかったもの」の除外事由の1つとして、省令では、医療従事者から事前に、患者、家族に死亡などが予期されていることを説明した場合があげられ、こうした説明がなされた場合には、「医療事故」にはならない取扱いです。したがって、「説明」の有無は、今後は、報告、調査義務の対象となる医療事故となるかどうかの重要な判断要素となります。
また、省令と同時に発せられた厚労省医政局長の通知(平成27年5月8日厚労省医政発0508号第1号)によれば、除外対象としての「説明」といえるためには、一般的な死亡の可能性についての説明では不十分で、当該患者個人の臨床経過などを踏まえて死亡等が起こりうることについての説明であることが、必要である旨、定められています。説明のあり方については、行政解釈としても、上記3で述べた判例と同様の、患者に応じた個別的な説明水準を求めていることを明らかにしているものです。(池田伸之 日総研出版「病院安全教育」2015・2016 12・1月号掲載)
※掲載誌についてのお問合せは下記へ
日総研出版(http://www.nissoken.com/)