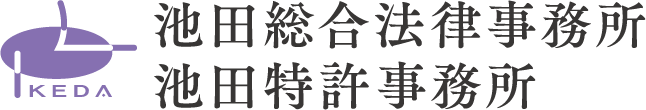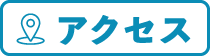情報流通プラットフォーム対処法(以下、情プラ法と略記します。)について (運用状況の透明化)― その2
令和6年5月17日に公布された情プラ法が、本日(令和7年4月1日)より施行されます。この間、総務省によりガイドライン(R6.3/11制定https://www.soumu.go.jp/main_content/000996607.pdf)が公表されております。今回は、先回に引き続き、運用状況の透明化についてお話します。
(1)判断基準の策定・公表(運用状況の公表を含む)について
SNS等で、どのような投稿が削除されたり、場合によってはアカウントが停止されるかどうかは、利用者にとっては重要な情報です。また、情プラ法が規制対象としている「大規模特定電気通信役務提供者」(以下、事業者といいます。)の行うサービスの利用者や投稿数は膨大な量となり、事業者の判断が、利用者の表現の自由に大きな影響を与え、また、被害者にとっても、削除の基準が明確になれば、被害情報が事業者によって削除されるかどうかの予見性が高められることになります。
削除基準について、行政が立ち入ることは、表現の自由を確保する観点から適切ではないので、従前どおり、事業者が自ら行うことを前提とする仕組みは維持し、ガイドラインの形で、その基準の具体化をはかっています。
違法情報ガイドラインによれば、①他人の権利を不当に侵害する情報(権利侵害情報)と②その他送信防止措置を講ずる法令上の義務がある(努力義務を除く)情報(法令違反情報)を含むものが送信防止(削除)義務の対象となります。
①の例としては、名誉権、プライバシー、私生活の平穏、肖像権、パブリシティ権、著作権、無体財産権、営業上の利益等が対象となり、
②の例としては、わいせつ関係、薬物関係、振り込め詐欺関係、犯罪実行者の募集関係、金融業関係、消費者取引における表示、銃刀法関係に関して、当該情報の流通が各法令に違反する場合が、その対象となります。
これらの基準は、事前に公表する義務が課せられ、情報の流通を知ることとなった原因別に、情報の種類を出来る限り具体的に定められていることや、利用者が容易に理解できる表現を用いること、基準について、その理解を助けるために、参考事例等を作成して公表することも求められています。
(2)削除した場合の発信者への通知
被害者の救済と表現の自由とのバランスから、発信者に対する削除またはアカウントを停止した場合には、その事実およびその理由を発信者に対して通知し、又は発信者が容易に知り得る状態に置く義務が課されています。これにより、発信者は、事業者に異議を申し立てて再考を促す機会を得ることにもなり、不当な削除については、事業者に対して民事訴訟で争う際の資料を得ることになります。
但し、例外的に、①過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により削除したことについて、既に通知等の措置を講じたり、②情報の二次被害を惹起する蓋然性が高い場合等、正当な理由のある場合には、通知等の措置は不要となります。
理由の通知にあたっては、その理由の説明をどの程度詳しく記載するか、発信者への分かりやすさの観点が重要であるとともに、悪意のある発信者による基準の潜脱に繋がらないようにすることへの配慮も必要です。いずれにしても、基準の具体的項目への該当性が示され、異議申立をする際の参考となる程度の具体性が求められることになります。
SNSには誹謗中傷、SNSを利用した犯罪や、犯罪への勧誘、詐欺が蔓延する中、今回の情プラ法の施行を受けて事業者が適切な対応をして、迅速に被害の拡大防止を計っていくことが、期待されます。池田総合法律事務所においても、SNSによる誹謗中傷等の相談を実施していますので、ご相談下さい。
(池田伸之)