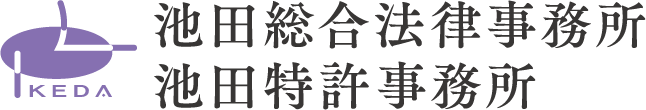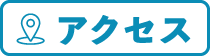最高裁判例⑤自筆遺言に関する最高裁判例のご紹介
遺言は公証人役場に出向く、または公証人に出張してもらって作る公正証書遺言も利用されますが、自筆遺言も大いに利用されています。これは、全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。
遺言はなくなってから権利義務が実現することになるため方式が法律に定められ、本人に確認することはできませんから、法定の作成要件を守らないと方式違反で無効ということになります。遺言がなければ法律の定める通り遺産分けをすることになりますが、遺言が残されていれば、その有効無効を先に決することになり、自筆遺言については残された相続人らの間で争われることが少なくありません。
今回は、控訴審判決を覆した最高裁判決について、ご紹介します。
ご紹介する事案では、自筆遺言証書に、真実に遺言が成立した日と相違する日付が記載されているからといって、遺言が直ちに無効となるものではないと、判断されたものです。これを参考に自筆遺言を作成するときの問題を考えてみたいと思います。
<事案の概要>
亡くなったAさんは、入院先の病院で、4月13日の日付の遺言の全文、同日の日付、氏名を自書し、退院して9日後の5月10日に、弁護士立ち合いの下、押印しました。Aさんの妻である上告人らが、遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張して、Aさんの内縁の妻らである被上告人らに対して、遺言が無効であることの確認等を求めました。
<最高裁の判断-令和3年1月18日第1小法廷判決>
原審は、遺言書に真実に遺言が成立したと相違する日の日付が記載されている方式違反により無効であるとしました。これに対して、最高裁は、入院中の日に自筆証書による遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後(全文等の自書日から27日後)に押印したなどの事実関係の下においては、自筆証書に真実に遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからと言って直ちにその自筆証書による遺言が無効になるものではない、と判示して、原審に差し戻しました。
遺言書に記載すべき日付けについては、遺言における要式行為性を重視し、法律行為としての遺言の成立日はすべての方式を充たした日とする考え方、と、意思表示を重視して全文自書した日の日付を記載すべきとする考え方があるかと思います。これまでも、複数の日にまたがって作成された遺言について、争われたこともありました。
日付の記載を欠いている場合は、方式違反になり無効となることは争いがありませんが、日付の記載はあるものの、誤って遺言成立日と相違する日付を記載した場合にも方式違反により常に無効となるのかも問題となります。
そもそも、自筆証書遺言の方式として、全文、日付及び氏名の自書並びに押印を要件とした法の趣旨は、遺言者の真意を確保することにあり、あまりに厳格に方式を考えなければならないとすれば、意思の実現が難しくなります。書き損じが明らかで、容易に判明する場合は無効とならない余地があります。また、書き損じではなく、遺言の成立日に関する認識が誤っていた場合には、具体的な事情や作成経過を検討しなければならないことになります。
本件で最高裁は、真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって遺言が無効になるものではないと判示しており、その上で、高裁に差し戻した理由は「本件遺言のその余の無効事由についてさらに審理を尽くされるため」としています。
最近では、法務局で、自筆で作成された遺言書を保管する制度もあります。遺言書の原本と画像データを法務局が保管する(保管期間は遺言者の死亡後50年間、画像は150年間)し、保管された遺言書は家庭裁判所の検認(相続人立ち合いの下、裁判官が開封し、検認の日の遺言書の内容を確認する手続き)が不要です。
遺言者が亡くなると、遺言の存在を相続人などに法務局からお知らせすることもできます。①指定者通知-遺言者が指定した人に遺言書が保管されていることを通知する、通知先は3つまで。②関係遺言者保管通知-死後にだれか一人でも相続人や遺言執行者など利害関係者が閲覧したり、遺言情報証明書を取得したら、全員に通知される制度があり、遺言の実現がスムーズになされるような制度改正がなされています。
もっとも、日付をはじめ、要件を充たして、遺言が有効となることが前提ですから、作成するときには、注意を払っていただきたいものです。
やむを得ず、自筆証書で遺言を作成する場合にも、遺言の文言など、内容の実現の確実性など、ご相談いただいた方が望ましいといえます。
(池田桂子)