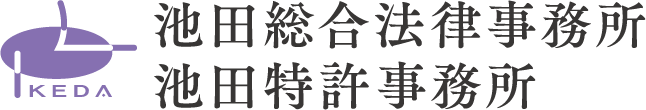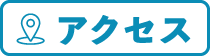財産分与に関する改正
1.はじめに
令和6年(2024年)5月、民法の家族法の一部が改正されました。令和8年(2026年)5月24日までに施行される予定です。
今回は、財産分与の改正について解説します。
2.財産分与
(1)財産分与の請求期間
従来、財産分与は、離婚から2年以内に請求することが必要でした。
しかし、婚姻期間中に夫からDV等を受けていたため、離婚後も恐怖心から元夫に対して財産分与の請求が出来なかったり、子どもが幼く育児等に追われ、財産分与を請求する余裕がなく、時機を逃してしまったなど、離婚の際の事情によっては、2年以内に財産分与の請求ができないこともあり、離婚後に一方当事者が困窮することになるなどの指摘がありました。
一方で、財産分与の期間を伸ばすことで、財産分与の請求時から財産分与の基準時(通常は、離婚時または別居時のいずれか早い時点)まで、相当長期間遡ることになるため、基準時における財産分与の把握が困難になるおそれがあり、紛争が長期化・複雑化するといった懸念があります。
以上の事情を踏まえ、今回の改正では、5年に伸長されることになりました。
なお、年金分割は、原則として、離婚をした日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります。今回の財産分与の期間伸長によっても、年金分割の手続期間は変わりませんので、注意する必要があります。
(2)財産分与の法的性質、2分の1ルール等
現行法では、財産分与の目的や考え方が定められていませんでしたが、今回の改正では、これらの点が一定程度明確になりました。
現行民法768条3項
| 家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 |
改正民法768条3項
| 家庭裁判所は、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため、当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。 |
今回の改正で、財産分与の目的として、「離婚後の当事者間の財産上の衡平を図る」ことが明示されるとともに、新たに追加された「各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入」の文言により、財産分与の法的性質として、清算的要素、扶養的要素、補償的要素を有することが明確になりました。
したがって、今後事案によっては、単純に財産額のみから財産分与額を決するのではなく、上記の事情についてもより積極的に主張していくことが考えられます。
また、財産分与における寄与の割合について、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」として、原則的には2分の1とすることが明記されました。
現在の実務においても、2分の1ルールについては既に定着しているところですが、これが条文に明記された形になります。
3.おわりに
財産分与は、離婚後に安定した生活を送るために、重要な制度です。夫婦の共有財産について出来る限りの調査を行い、必要な主張を尽くすことで、最終的に得られる財産分与の額が変わる可能性もあります。
どのようなことを調査するのか、その手掛かりは何かなど考えるポイントがありますので、お悩みの方は池田総合法律事務所までご相談ください。
(石田美果)