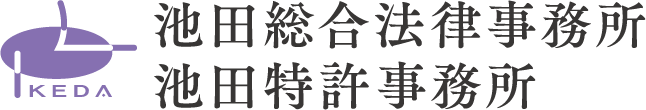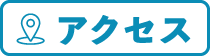離婚後の子どもの監護(養育)に関するルールについて
令和6年5月の家族法改正により、これまで離婚後は認められていなかった「共同親権」が可能になりました。この記事では、共同親権の選択方法や行使方法、離婚後の子どもの監護(養育)に関するルールについて解説します。
1 離婚後も「共同親権」を選択可能に
改正前は、父母が離婚した場合、どちらか一方のみを親権者と定める「単独親権」しか認められていませんでした。しかし、改正により、離婚後も父母双方を親権者と定める「共同親権」を選択できるようになります。これは、父が認知をした子どもについても同様です。
具体的には、協議離婚や調停離婚の場合、父母の話し合いにより、共同親権とするか単独親権とするかを決定します。協議が調わず裁判離婚となった場合には、家庭裁判所が父母の子どもとの関係や生活状況などの様々な事情を考慮し、子どもの利益に照らして親権者を決定します。ただし、虐待やDVのおそれがある場合など、共同親権と定めることで子どもの利益を害すると判断されるときは、必ず単独親権と決定されます。
また、改正により、子ども本人やその親族は、親権者の変更として、父母の一方の単独親権から他の一方の単独親権だけではなく、単独親権から共同親権、共同親権から単独親権に変更することを請求できるようになります。家庭裁判所は、親権者を定める協議の経過やその後の事情変更を考慮して、子どもの利益のため必要があると判断した場合に、親権者の変更を認めることになります。
例えば、離婚前に父母の一方が他方に対して暴力をふるっていたようなケースでは、対等な立場での話し合いができず、やむを得ず暴力をふるっていた一方を単独親権と定めることが考えられます。そのような場合には、子ども本人やその親族は、離婚後に家庭裁判所に対して親権者の変更を請求し、協議の経過や事情変更を考慮してもらうことで、不適正な合意がなされたケースに対応することができます。
なお、改正前に離婚して単独親権と定めた場合には、改正により自動的に共同親権に変更されることはありませんが、改正後に家庭裁判所に対して親権者の変更を請求することにより、共同親権への変更が認められる可能性があります。
2 共同親権の行使方法
共同親権と定めた場合、原則として、父母が共同して親権を行使します。ただし、実際の子育てではすべてを父母で話し合って決定するのは現実的ではないため、一定の例外も設けられています。
例外的に父母の一方が単独で親権を行使することができるのは、監護教育に関する日常の行為をするとき(例:食事や服装の決定、習い事)や、子どもの利益のため急迫の事情があるとき(例:DVや虐待からの避難、緊急の医療対応)です。
また、上記の例外に当たらない事項で、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所に対して、その事項に限って親権を行使する親を指定してもらうよう請求することができます。
3 離婚後の監護(養育)のルールが明確に
離婚の際、子どもの利益を最優先に考慮して、父母で子どもの監護の分担を定めることができます。例えば、平日は父母の一方が子どもを監護し、土日祝日は他方が担当するといった取り決めが考えられます。
また、父母の一方を「監護者」と定めることもできます。共同親権と定めたとしても、実際に子どもと暮らすのはどちらか一方だけというケースも考えられます。そのような場合には、父母の一方を「監護者」と定めることで、監護者に子どもの監護を委ねることができます。監護者は、日常の行為に限らず、子どもの住まいや育児方針などを単独で決定することができるようになります。監護者でない親権者は、監護者による監護の妨害をしてはなりませんが、妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに一時的に子どもの監護をすることができます。
家族法改正は、令和8年5月までに施行されます。今回の改正により、離婚後も父母がともに親権者として子どもに関わる「共同親権」の選択肢が広がり、親権や監護に関するルールがより柔軟かつ明確に定められるようになりました。これにより、離婚後も子どもの利益を最優先に考えた子育てが可能となり、父母双方の協力のもとで円滑な子育てが実現されることが期待されます。ただし、制度を活かすには父母の理解と協力が不可欠です。トラブルを防ぐためにも、弁護士など専門家のサポートを受けながら、子どもの利益を最優先に考えた親権・監護のあり方を選択していきましょう。
(栗本真結)