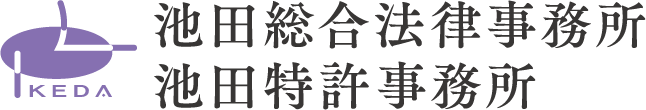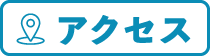野上陽子の摩天楼ダイアリー⑩
2021年6月、ニューヨーク にて。コロナ感染を考える
ニューヨーク州から市民宛に送られてきたEメールを訳してみました(そのEメールの原文(一部)は末尾にありますのでご覧ください)。
2020年初め緊急事態宣言後から今まで州知事から毎日来ていたemailは、「親愛なるXXXさん」で始まります。
「本日、パンデミックの緊急事態を解除し、ニューヨークのCOVID-19非常事態宣言は終了しました。 しかし連邦CDCガイダンスは引き続き実施されます。つまり、ワクチン接種を受けていない場合は、屋内の公共の場ではマスクを着用する必要があります。 公共交通機関や医療施設などの特定の場所では、マスクは引き続き必要です。 COVIDとの戦いとニューヨーカーへの予防接種は依然として私たちの最優先事項ですが、緊急事態は終わりました。これは、ニューヨーカー、特にすべての重要な労働者の努力のおかげです。私たちは、COVIDの回復と、ニューヨークの再考と再建に引き続き注力していきます。」
緊急事態宣言後、生活に必要な食料品店以外はすべて閉店。美容院、ネイルサロン、もちろん洋服店などは当然閉店でした。マンハッタンは、劇場も映画館もホテルもすべて閉鎖、娯楽は全くなくなりました。寂しいという感じは全くなく、緊張した日が続きました。今は、すでに博物館や美術館は定員制限の予約制ですが開館しました。もうすぐブロードウェイも戻ってきます。
去年を思い出すと、公共交通も医療従事者や食料品の従業員など、必要不可欠な人以外は使わないようにと告知され、6か月間は、事務所は自粛閉鎖。去年の秋から、事務所まで徒歩30分ほど、途中の道は、誰にもすれ違うことがなく、車が走っていないため信号機が不必要でした。当時、事務所にも人がいませんが部屋を出る時は、マスクをして、ドアやノブを触る度に消毒は欠かせませんでした。
マーケットは人数制限をして、床には一方通行の印が有り、並ぶときには2メートル間隔で並ぶように床には印があります(今もあります)。エレベーターはサイズに関わらず3人まで、アパートのエレベーターは2人まで、皆我慢をしていました。買い物かごは、部屋に即持ち込まず、半日や1日置きっぱなしにして感染を防いでいました。
ここまでしなければ ダメなのかしら?と思うかもしれませんが、こうした防御は、自分を自分で守る方法でした。私の住んでいるビルからも感染者が出ましたし、ビルの管理者も感染しました。感染はすぐそばにあるもので、でも見えないもので、対策をとっても感染してしまう可能性がありました。
 あれから1年半が経ち、ワクチンが進み、事務所のビルはマスクなしで入れます。エレベーターは3人から4人まで乗れます。事務所内でもマスクなしで過ごせるようになり、事務所の住人の笑顔が見えます。それでも習慣化したマスクやデスタンスは残っています。
あれから1年半が経ち、ワクチンが進み、事務所のビルはマスクなしで入れます。エレベーターは3人から4人まで乗れます。事務所内でもマスクなしで過ごせるようになり、事務所の住人の笑顔が見えます。それでも習慣化したマスクやデスタンスは残っています。
ニューヨークでのワクチン接種は、2021年1月から始まり、75歳以上の高年齢者、医師や医療従事者(高年齢者施設の職員も含む)、そしてその2週間後には、65歳以上の市民、マーケットの従業員、公共交通従事者、警察官、消防士らの接種が始まりました。予約はインターネットで行い、年齢が判る身分証明書(人によっては職種証明書や雇用証明など)を持って接種所に向かいました。場所は幕張メッセの様な大きな施設(週末は、州の学校)を会場にしていました。私の接種時に一緒になった若い人たちは、職業の証明書を見せていました。
どのくらいの勢いで接種が進むのかが気になっていましたが、かかりつけの医師や病院の関係者、その次に、マーケットのレジのお姉さん、食料品を運んでくるトランクのおじさん、バスの運転手、地下鉄の運転手など、24時間働いて普段の生活を支えてくれる人達が高年齢者と一緒に接種が進み、生活を支えてくれている人たちが受けられて、本当にほっとしました。
今は誰でも即接種ができます。PCR検査も同じように移動車が回っています。どちらも気軽にその場で受付してもらい無料です。徐々に通常の生活に戻ってきている感じがします。車の渋滞を見ますし、朝の通勤ラッシュで人が多く移動しています。
マンハッタンの接種率は、大変高いですが、でも全員ではありません。それに、他の州からの訪問者もいます。通勤で使うバスの中には、マスクを外している人をたまに見ます。不愉快と感じているのは私だけではないようです。
マーケットでは、接種をした人はマスクが不要といいますが、自己申告で本当のところはわかりません。マスクをしていない人に限って、マスクの件を指摘されると、自分は接種していると言い張ります。同時に、お店のレジの人達は、緊張して笑顔が消えます。レストランやバーではもちろんマスクを外していますが、お店の人たちは、マスクをしています。
もちろん病院では、全員マスク着用です(これは今後長きにわたり残ると思います)。こうしてニューヨークのマンハッタンのことを書いていますが、では米国全体としてどうなのでしょう?
米国では、自分の身は自分で守る。個人の意志を尊重する考え方があります。ここに住み始めて、よく聞かれたのは、「あなたは、どうしたいの?」という言葉でした。その通りにならないとしても自分の思いを言うようにとよく言われました。
宗教、個人の考え、体調、どんな理由であれ、接種は強制できません。もちろんインフルエンザや他の接種についても同じです。今回は政治的な背景があるようですが、それも個人が判断することです。
日本からの訪問者だけでなく、多くの国から米国に入国する人たちも、国内での移動時など、他人が1メートル以内に長い間いるような移動は、気になるようです。私も気になります。私が気になる理由は、もしかしたら2020年の3月ごろ、同じ事務所を使っていた人がマイアミに行き、機内で感染して2週間後に亡くなったせいかもしれません。40歳ぐらいでがっちりとした体格の健康そうな人でした。誰もが驚きましたが、どうにもなりません。本人が一番驚いたと思います。
世界中を巻き込んでいる感染ですから、国内に持ちこませまいとすべてのことを遮断していても日本に入って来てしまうでしょう。
インドもEUも他のアジアでも感染はどこでも起きています。パスポートで母国に帰る理由で行き来する渡航者、ニューヨークの様に二重国籍の多いところでは、人の動きを止めるよりも、できる限り接種して、感染犠牲者を防ぎたいと考えていると感じます。誰が接種完了したか判りませんから。
先日、ブルース・スプリングスティーンのコンサートがあり、入場には、チケットと身分証明、それに2回の接種完了の証明がないと会場に入れない、という方法が取られました。接種証明書は、アメリカでは反対派が多く、実現しないと言われていますが、ニューヨーカーはニューヨーク独自の接種証明書をApp化しています。
ここ世界中の人が住んでいるニューヨークでは、確実に死者や感染者が減少しています。6月24日発表では、ニューヨーク州人口20,759,365人中、PCR検査113,108人中343人の感染、死者は5人、入院中442人です。
6月28日発表では、PCR検査55,334人中、290人の感染確認、死者は3人、入院中346人でした。
感染者や患者の中で、ワクチンを打っていない人が多いのもまた事実です。
今後、出張や旅行、すべての移動に制限を付けてはいられません。観光大国は日本だけではなく、マンハッタンもパリもミラノも観光は、大きな経済の支えです。オリンピックイベントだけではなく、海外アーテストのコンサートやオペラ、演劇など、多くの海外からの文化を遮断することはできないと思うのです。
何十年も前の話ですが、私は、日本を出る時に予防接種をしました。米国入国時に接種をしていなければ入国できなかったのです。そんな時代もあったのです。
私は(もし陽性だとしても)人に移したくないし、これ以上知り合いで亡くなって欲しくないです。味覚障害や臭覚障害は、一度なってみないと判らないことですが、とても辛いでしょう。体調不良や呼吸疾患なども治る保証はありません。
以上、ニューヨークで改めて考えさせられたことを書きました。ニューヨークで事業展開や投資業務のお手伝いをしている私ですが、安全・安心の下、ビジネスを進めていかなければなりません。現地情報が必要な方々は、私の会社窓口までお尋ねください。いつでもお気軽にお尋ね頂ければ幸甚です。
野上陽子(ニューヨーク市マンハッタン在住、コンサルタント会社を経営)
サイトのご案内 https://www.ynassociates.net/
New York StateからのMailの原文(一部分)
June 24, 2021.
Dear Yoko,
Today we close out the emergency chapter in the pandemic—effective today, New York’s COVID-19 State of Emergency has ended. Federal CDC guidance will remain in place, meaning if you’re unvaccinated, you should still wear a mask in public indoors. Masks will also still be required on public transit and certain other settings, like health care facilities. Fighting COVID and vaccinating New Yorkers are still our top priorities but the emergency is over—and that’s thanks to the hard work of New Yorkers and especially all our essential workers. We will continue to focus on COVID recovery and reimagining and rebuilding New York.
- COVID hospitalizations are at 442. Of the 113,108 tests reported yesterday, 343, or 0.30 percent, were positive. The 7-day average percent positivity was 0.35 percent. There were 101 patients in ICU yesterday, down one from the previous day. Of them, 60 are intubated. Sadly, we lost 5 New Yorkers to the virus.
- As of 11am this morning, 71.3 percent of adult New Yorkers have completed at least one vaccine dose, per the CDC. Over the past 24 hours, 56,547 total doses have been administered. To date, New York administered 20,759,365 total doses with 63.5 percent of adult New Yorkers completing their vaccine series. See additional data on the State’s