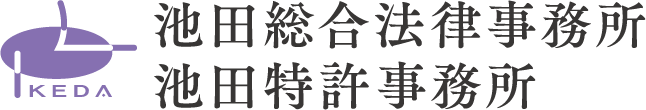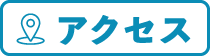相続税の計算は、「相続税について」で述べたように一定範囲の相続財産から、法定のものを控除して、残った金額に応じて所定の相続税率を掛け、そこから一定額を控除するものですので、節税対策として、突き詰めると、
(1)財産を減らす(評価を下げることを含めて)
(2)控除項目を活用する
に尽きます。
それぞれについて、どのような方法があるのか、また、どのような点に注意をすべきか、以下にその一部をご紹介します。
(1)財産を減らす
①生前贈与の活用
生前贈与には、1年毎に精算する暦年贈与と相続時精算課税があり、暦年贈与は、年110万円までの基礎控除があり、この範囲内では毎年親族はもとより、それ以外の第三者に贈与する場合にも、無税です。また、これを超えても年310万円未満までは、年10%の課税で済みますので、節税対策となります。
②住宅取得資金の贈与(非課税枠の利用)
直系尊属(父母、祖父母)が住宅取得資金を20歳以上の子や孫に贈与したときは、一定要件(床面積要件、受贈者の所得要件等)の下、建物が省エネ、耐震住宅かどうかによって、基礎控除も加えて、910万円から3110万円(省エネ、耐震住宅)または410万円から2610万円(それ以外の住宅)の限度で非課税となります。住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合には、基礎控除も加えて、1310万円から3110万円(省エネ、耐震住宅)または810万円から2610万円(それ以外の住宅)の限度で非課税となります(当面、平成33年12月までの措置)。住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日によって控除額は大きく違いますので、非課税要件の有無も含め詳細は、弁護士、税理士等の専門家にお尋ね下さい。
③教育資金の贈与(非課税)
直系尊属から、30歳未満の子や孫への教育資金は1500万円まで、非課税となります(但し、30歳(受贈者が在学中であれば教育資金の非課税措置の期間を40歳まで延長可能)に達した時に残りについては、贈与税が課せられます。)。もっとも、この制度を利用するためには、銀行や信託銀行などで「教育資金口座」を開設する必要があるなど、一定の手続が必要となりますので、注意が必要です。また、贈与時に申告が必要です。
④結婚、子育て資金の贈与(非課税)
直系尊属から20歳以上50歳未満の子や孫で結婚、子育て等の使途のための贈与は、1000万円(但し、結婚資金は300万円まで)まで非課税となります(但し、50歳に達した時の残額については、贈与税の対象となります。)。なお、贈与時に申告が必要です。
⑤扶養義務者による教育費、生活費の負担
直系尊属又は兄弟姉妹は、法律上扶助義務を負っていますので、教育費や生活費で通常必要と認められるものは、限度額の制限なく非課税であり、生前贈与加算はありません。扶助義務の履行で贈与ではないので、当たり前といえば当たり前です。
したがって、③や④については、この制度を利用して一括して贈与するのではなく、この方法でも十分対応可能と思われます。扶助のレベルは、それぞれの収入・資産等の生活状況によって大きく異なり、生活レベルと比較して、相当高額なレベルでなければ、結婚等のための贈与が、贈与として問題とされることは、ほとんどないと思います。子や孫のために、結婚や進学などの都度、金を出すことは、通常、問題となりません。
⑥居住用財産の贈与
婚姻期間が20年以上の配偶者が、他方に対し居住用不動産又は、居住用の不動産を購入するための資金を贈与した場合は、2000万円まで(基礎控除と合計すると2110万円まで)、非課税となります。死亡前3年間の贈与については、通常、相続財産の中に入れて、相続税が計算されてしまいますが、この贈与については、2000万円までは、そうした扱いがなされることはありません。なお、この特例を受けるためには贈与税の申告が必要です。
⑦評価を下げる
相続財産の評価は、対象となる財産によって、大きく違ってきます。
現金、預貯金などは、額面そのままで評価されますが、土地は路線価、建物は固定資産税課税台帳上の評価額により時価よりは通常低い金額で評価されます。
従って、現金等を不動産に転化することは、遺産の評価を下げることになり、有効な節税対策となります。
また、居住用土地や特定事業用、貸付事業用の宅地のうち、小規模なものは使用目的、面積に応じて、50~80%までの評価減がなされ、さらに節税効果があります。
自己所有地に、賃貸物件の建物を建て、これをアパートとして貸すことによって、大きな節税効果が得られる反面、大きなリスクを伴います。
税制の「個人は増税、法人は減税」という大きな流れの中で、上記の方法に相続人らが設立した会社に賃貸をするというスキームを加えたものも、紹介されていますが、これについてもリスクがあります。さらに、①相続開始が迫っている時には、節税効果も高くなく、②この会社が建物を簿価で買うことになりますが、その代金の返済も大変で、買受代金が相続時に残っていれば、それも相続財産となってしまうので、節税効果が上がらないこともあります。
また、③代金の返済は、経費として損金扱いとならないため、残代金返済を早期にもくろむと利益が生じ法人税が発生します。
こうしたスキームは緻密な計画と将来予想が不可欠で、専門家の相談を受けたうえで行うことが不可欠です。
(2)控除項目を増やす
①法定相続人を増やす
養子をとったり(実子があるときは、1人だけ、実子がないときは、2人まで、なお、例えば妻の連れ子を養子にした場合等は、実子扱いとなります。)、正式に結婚することは、基礎控除の相続人比例部分を1人当たり600万円増やすことになり、配偶者の場合には、配偶者控除という強力な節税手段を得ることで、節税効果は、絶大です。
ただし、これは、注意をしないと、「争族」の元となります。
①生命保険金の活用
被相続人×500万円の非課税枠があり、死亡時に受け取れる終身保険金が最適です。
①法定相続人を増やす
被相続人の債務も、相続税の計算上控除されますので、債務を負担することは、節税対策となります。ただし、財産だけではなく、債務も相続人にも承継されてしまうので、節税にはなったが、巨額の債務が残ったということであれば、何をやっているかわかりません。自己所有地に借入で建築資金を賄い、賃貸マンションを経営するスキームであれば、ここでも借入金控除が大きな節税効果となっています。相続開始後も承継した借入金が無理なく返済していけるのかどうか、十分な検討が必要です。