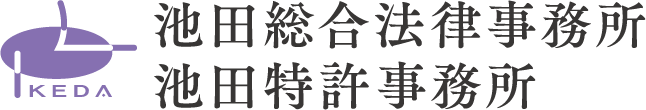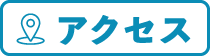遺言記載の事項は、全て「有効」でしょうか。―法定遺言事項と「付言事項」―
遺言の中には、さまざまなことが記載されたものを見かけますが、そこに記載されていることは、全て法律的に意味のあることなのでしょうか。法的な効力をもつ遺言事項は、主に民法(相続法)に記載されており、「法定遺言事項」といいます。それ以外の事項は、法的な効力を有するものではなく一般的に「付言事項」といわれています。
法定遺言事項には、①「~の相続分を3分の2、~の相続分を3分の1とする」というような「相続分の指定」や「~の不動産は、~に相続させる」等とする「遺産分割の方法の指定」等の遺産の処分に関する事項と、②「~を認知する」という「子の認知」(生前ではなく、遺言による認知で「死後認知」といわれています。)、「相続人の廃除(後述)」等、相続人の確定に関する事項があります。
他方で付言事項の例としては「~には死亡保険金の受取人となっており、その点を考慮して、遺産の配分を決めたもので、その点を理解、納得してもらいたい。」といった例があります。
さて、付言事項は、法的な効力を有するものではないのに、なぜ、わざわざ遺言に記載しておくのでしょうか。
例えば、法定相続分と異なり特定の相続人に大きな財産を相続させる場合等は、そのような遺言を残すに至った経緯を記し(前述の例がそうです。)、他の相続人の理解を得ようとして書かれることがあります。それが、期待した効果を有するかどうかは、それまでの人間関係如何によって、大きく左右され、こう書いたから他の相続人が納得するかどうかはわかりません。
例えば、遺留分を侵害される可能性のある相続人に向けて「こうした事情があるから、~は、遺留分の権利主張をしないで欲しい。」と書かれている遺言もよくみかけます。しかしながら、こうした記載は法的には意味はなく、却って相続人を感情的に刺激して、相続人間の対立をあおる結果となることが多いのが実情です。
また、別の例として、「~は、散々に親不孝を重ねてきたので、相続分はない。」という遺言はどうでしょうか。相続分はないといっても、兄弟姉妹(やその代襲相続人)を除く相続人には、遺言でも侵害できない遺留分という相続人としての最小限の権利が留保されており、侵害された相続人は、遺留分に相当する金員(令和元年7月1日以降開始の相続)、又は、相続財産に対する遺留分相当の共有持分(同日より前に開始した相続)の請求または、返還を請求できる権利があり、その限度で、遺言の効力を失わせることができます。
こうした場合に遺留分まで取り上げるためには、遺言で相続人としての地位を「廃除」する意思を表示しておく必要があり、上記の記載では不十分で、明確に廃除の意思表示をしておく必要があります(廃除の手続き等については、後日アップします。)。
法定遺言事項は、法律上明確に、「遺言で~できる。」と規定されている場合が多いのですが、遺言でできることは、それに限られるわけではありません。
たとえば夫婦関係が、妻の浪費で折り合いが悪い中、未成年の子に多くの財産を残し、妻の子に対する財産管理権を奪うことが遺言で出来るでしょうか、民法830条は、「無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にそれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属さないものとする。」と規定されています。解釈上争いはあるものの、この「第三者」には、親権者を含み、財産を無償で与える行為の中には、遺贈も含まれると解されており、「遺言で」という記載ではないものの、遺言でこのように子が相続した財産に対する親権者の管理権を制限することができます。
遺言で出来ることは、民法(相続法)だけに記載されているわけではありません。保険について、知っておいて頂きたいことがあります。保険金の受取人の変更が法改正により、できるようになり、これは、保険法に規定されています(第44条)。
遺言が効力を生ずるのは、ご本人が死亡をした後のことであり、遺言の解釈にあたっては、背景事情なども含めて遺言者の意思を「忖度」することになりますが、その記載内容それ自体が最も重要な点で、その記載内容の如何で、法的な効力が失われたりしますので、作成にあたっては、専門家への相談が不可欠です。当事務所では、このようなご相談にも対応しています。(池田伸之)