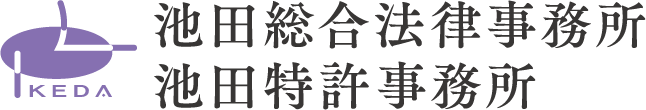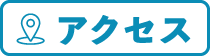副業・兼業について(労働者側の注意点)
厚生労働省は、平成30年1月に、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しました。このガイドラインは、令和2年9月、令和4年7月の2度に渡って改訂されています。このようなガイドライン策定・改訂は、働き方が多様化する中で、ルールを明確化することにより働く方が安心して副業・兼業に取り組める環境を整備するためのものです。
副業・兼業のあり方は雇用、業務委託、起業の組み合わせによって様々な形式がありますが、ここでは既に雇用されている労働者を念頭に、別の仕事を掛け持ちする場合に注意すべき点について説明します。
会社に雇用されている方が副業・兼業を始めようとする場合、まずは既に働いている会社(会社での業務を「本業」と言うことがあります)の就業規則や雇用契約書において、副業・兼業が可能か、また可能だとしてどのような手続が必要かを検討する必要があります。
なお、労働基準法では、原則1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないこと等の労働時間に関する規制がなされているところ、本業と副業・兼業のそれぞれの労働時間を合算した時間が当該労働者の労働時間となります。そのため、形式上手続を踏めば副業・兼業が可能な場合でも、フルタイムで働いている場合には実際には本業への影響を懸念して副業・兼業が許可されなかったり、禁止されたりすることがありえます。このような場合には、元々の雇用契約上の労働日や労働時間を減らすなどの交渉・調整が必要となるでしょう。副業・兼業の経験やスキルが本業にも活かせると示すことや、自身の有する職務上の権限やノウハウ等の引継期間を調整するなどして準備をすることなどが必要でしょう。
副業・兼業では、労働者として留意すべき点があります。
まず、働く時間が長くなる可能性があるため、働く側で自律的に労働時間や体調を管理する必要があります。副業・兼業の場合、働く側が就業先に労働時間を自己申告することになります。そのため、無理に過重な労働をしようとすれば無理ができてしまいますし、場合によっては事情が変わって当初の申告と実際の副業・兼業による労働時間が乖離してしまうこともあるでしょう。その場合、少なくとも正確な労働時間の訂正の申告をしていないことによる処分のおそれがありますし、無理がたたって本業での働きぶりに悪影響が出れば、職務専念義務との関係でも問題が生じます。
また、本業での処分との関係では、秘密保持義務には注意を要しますし、本業と関連する業務を副業とする場合には競業避止義務にも配慮が必要です。
さらに、雇用保険との関係でも注意が必要です。1週間の所定労働時間が20時間より短い業務を複数行う場合には、実際の通算労働時間は長いのに、雇用保険の対象とならないという事態も有り得るので注意が必要です。その他にも、雇用保険に加入している会社を退職したとき、副業を続けていると失業給付の対象外となる場合があります。具体的には、離職票をハローワークへ提出し、求職の申し込みをした時点で副業を週20時間以上している場合は失業の状態とみなされず、失業保険の給付を受けられません。
加えて、求職の申し込み後から通算7日間の待機期間中は、副業することも禁止されていますので、待機期間中に副業をしてしまって不正受給にならないよう注意が必要です。
(山下陽平)