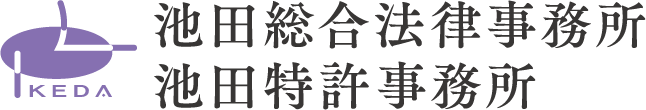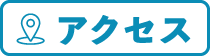1 交通事故にかかわる民法の改正点
平成29年5月、「民法の一部を改正する法律」が成立し、120年ぶりの大改正と大きく報道されました。その改正民法が、令和2年4月1日から施行されました。交通事故の損害賠償請求についても、4月1日をもって、適用されるルールが変わりました。
交通事故の損害賠償請求にかかわる大きな改正点として、①消滅時効に関するルール、と②法定利率に関するルールが挙げられます。以下、説明しましょう。
2 消滅時効に関するルールの変更について
(1) 人的損害の消滅時効の期間が3年から5年に改正されました
ア 損害賠償請求権を行使できるようになった時、具体的には損害および加害者を知った時から一定期間が経つと、消滅時効が完成し、相手方は消滅時効の完成を主張して損害賠償をまぬがれることができるようになります。今回の改正によって、時効完成までの期間が一部3年から5年に変わりました。
改正前の民法では、「人的損害」も「物的損害」も時効期間に区別はなく一律に、損害賠償請求権を行使できるようになってから3年で、時効が完成するとされていました。なお、「人的損害」とは、生命身体に関する損害、具体的には治療費、けがや後遺症の慰謝料、休業損害などのことで、「物的損害」とは、自動車の修理費用、レッカー費用、レンタカー費用などのことです。
イ 一方、改正民法は人的損害に関してのみ特別に、権利を行使できる期間を3年ではなく5年に変更しました(物的損害は3年のまま)。
交通事故を含む不法行為が問題になる場面では、死亡に至ったり、寝たきり等の重い後遺障害が残るケースなど、人的損害の方が被害が大きく深刻になりやすいこと、また深刻な被害が生じた場合に速やかな権利行使が期待できないという事情があることを考慮したものと考えられます。
ウ また、損害賠償請求権を行使できるようになった時(「主観的起算点」といわれます)から進行する時効期間内でも、交通事故日や後遺障害の症状固定日等の「不法行為時」(「客観的起算点」といわれます)から20年を超えると、請求できません。この点については、改正前も後も同じです。
(2) その他関連事項
ア 人的損害の場合、改正前民法の3年の時効期間の間に、改正民法施行日である令和2年4月1日を迎えるケースもありますが、このようなケースは改正民法が適用されます。
イ また、時効に関しては、時効の中断及び停止の事由が、時効の更新及び完成猶予の事由に再編成されました。従前の規定を引きついだ、時効の完成猶予に当たる訴訟提起や時効の更新にあたる判決の確定や承認等については、打つべき手立てが改正の前後で大きく異なるということはなさそうです。
特筆すべきは、改正民法では完成猶予に関して、当事者間で権利に関する協議を行う旨の書面による合意があった場合に時効の完成を猶予する制度が新設されたことです。この制度によって、時効完成直前に時効完成を防ぐために慌てて訴訟提起や調停申し立てなどの手続きを取るような負担が軽減される場面があるかもしれません。
3 法定利率の変更とその影響について
(1) 法定利率の変更と遅延損害金の減少
利息が発生するような請求権について、交通事故のように事前に利率を当事者が定めていない場合の利率(「法定利率」といいます)が5%から当面3%に変更され、遅延損害金や中間利息控除の対象となる逸失利益の金額が増減することとなりました。なお、法定利率は3%に固定されず、市中金利に合わせた3年ごとの変動制です。
交通事故による損害賠償も、実際に支払われるまでに長い時間がかかることがあります。そのような場合、交通事故の時点から法定利率による遅延損害金を請求することができます。遅延損害金については、5%から3%に引き下げられることによって、改正前と比べると同じ期間支払いが遅れた場合に請求できる遅延損害金の額は減ることになります。
(2) 法定利率の変更と逸失利益の増加
ア 一方で、逸失利益に関しては、法定利息の引き下げによって、改正前と比べると請求できる金額が増えます。なお、ここで、逸失利益とは、交通事故による損害賠償で、後遺障害が残った場合などに、毎年の収入のうちの一定割合が失われたとして、損害賠償の対象となる利益の減少分のことです。請求できる逸失利益額が増加するのは、中間利息控除に法定利率がかかわってくるためです。
イ まず、将来の受け取る利益を現在の価値に換算する方法と利率の関係について説明します。
今現在手元にある100万円と、1年後にもらう100万円とを比べると、今手元にある100万円の方が価値があります。というのも、仮に利率が年5%だとすると95万2380円を1年運用すれば約100万円になるからです。この場合、95万2380円は、利率5%の場合の1年後の100万円の現在価値といえます。
952,380×1.05≒1,000,000
なお、上記の数式から、95万2380という現在価値は、1年後の将来の利益額100万を利率5%で割り引く、つまり1.05で割ることでも求めることができます。
1,000,000/1.05≒952,380
また、現在価値は、1年後の将来取得すべき利益から、利益を得るまでの期間の利息(「中間利息」といいます)を控除したものと言い換えることができます。
952,380×1.05 ≒1,000,000
(952,380×1)+(952,380×0.05)≒1,000,000
(952,380)+(47,619) ≒1,000,000
952,380 ≒1,000,000-47,619
仮に法定利率が3%の場合を検討すると、100万円を利率3%で割り引いた97万0873円が、利率3%の場合の1年後の100万円の現在価値ということになります。
1,000,000/1.03≒970,873
利率5%の場合の現在価値は95万2380円、利率3%の場合の現在価値は97万0873円となり、法定利率が低く中間利息が少なくなるほど、逸失利益が増加します
ウ 以上の説明は、1年後の収入だけに限定した説明です。
例えば10年間にわたり収入失われる場合には、1年後の収入の現在価値だけでなく、2年後の収入の現在価値、3年後の収入の現在価値・・・10年後の収入の現在価値をそれぞれ計算し、合計することになります。
先ほどの例にそくして、年収100万円が10年の間失われるということになると、1年後の収入を割り引いたもの(1,000,000/1.05≒952,380)、2年後の収入を割り引いたもの(1,000,000/(1.05)^2≒907,029)、3年後の収入を割り引いたもの、・・・・10年後の収入を割り引いたもの(1,000,000/(1.05)^10≒613,913)の合計が損害額となります(X^2は、Xの2乗の意味です)。
このような計算をすべて行うのは大変なので、損害の算定の際には、複利の年金原価係数(ライプニッツ係数)を使います。なお、年利5%の場合の10年間のライプニッツ係数は7.722 なので、逸失利益の額は772万2000円となりますし、年利3%の場合の10年間のライプニッツ係数は8.530なので、逸失利益の額は853万円となり、法定利率の差によって、賠償額に大きな差が生じます。
4 以上が、民法改正が交通事故による損害賠償請求に与える影響です。
被害者にとって、人的損害について消滅時効の期間が長くなったのは有利な改正だったといえるでしょう。また、事故で大きなけがをして後遺障害が残ったという場合には、法定利率が引き下げられたことによって、結果として逸失利益額が増加することも少なくないでしょう。
とはいえ、改正前後のどちらの法律が適用されるかは被害者の側で選択できるようなものではなく、適正な賠償を得るために改めて特別の手段を講じなければならないといった影響はなさそうです。
民法改正前と同様、実際に適正な賠償を得られるかどうかは、事故直後から適切な治療を受けているか、後遺障害診断書に適切な記載があるか、また、適切な時期に弁護士が介入しているか等の事情によるといえます。
というのも、後遺障害が認められるか否かには後遺障害診断書に適切な記載がなされているかが重要であり、また、相手方保険会社は被害者本人との交渉では裁判で認められる和解金額よりも低廉な和解金額の提案をすることが多いからです。交通事故に遭われた方には、早期に弁護士に相談することを強くお勧めします。
弊所(池田総合法律事務所)では、経験豊富な弁護士がそろっていますので、お気軽にご相談ください。
〈山下陽平〉