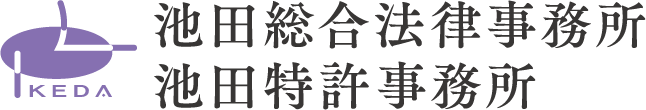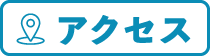下請法改正(1)
下請法改正の概要
「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」(改正下請法)が令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布されました。施行日は令和8年1月1日とされています。
改正により、従来の「下請代金支払遅延等防止法」という名称は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:取適法)に改められます。
近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、事業者がこの原資を確保する必要があります。そして、中小企業をはじめとする事業者が各々賃上げの原資を確保するためには、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが重要と考えられます。今回の改正は、発注者と受注者の対等な関係を基盤に、事業者間の価格転嫁や取引の適正化を進めることを目的としています。
主な改正内容としては、規制内容の追加(価格協議の義務化、手形払等の禁止)、適用範囲の拡大(特定運送委託の追加、従業員数基準の導入)を中心に、執行の強化、法律名・用語の変更などが含まれています。
本記事では、規制内容の追加、法律名・用語の変更、及びその他の改正事項について、詳述します。
なお、改正により法律名・用語の変更がなされていますが、混乱を避けるため、本記事では従来の用語(「下請法」「下請事業者」「親事業者」等)を使用しています。
1 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(取適法5条2項4号)
近年のコスト上昇の中、協議することなく価格を据え置いたり、コスト上昇に見合わない価格を一方的に決めたりするなど、上昇したコストの価格転嫁が問題視されています。
改正前においても、「買いたたき」(発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金を不当に定めること)は禁止されていました。しかし、通常支払われる対価とは同種又は類似品等市価を指すため、買いたたきに該当するかを判断する際には、市価の認定が必要となります。買いたたきとは別途、対等な価格交渉を確保する観点から、適切な価格転嫁が行われる取引環境の整備が求められています。
そこで、改正により、親事業者が、下請事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、親事業者が必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に下請代金を決定することが禁止されます。
例えば、運送会社A(親事業者)が、運送会社B(下請事業者)から代金の引き上げについて協議を求められたにもかかわらず、これを無視して協議に応じなかった場合や、機械メーカー(親事業者)が、部品メーカー(下請事業者)から代金の引下げの説明を求められたにもかかわらず、具体的な理由の説明や根拠資料の提供をすることなく、代金の額を引き下げた場合などが該当し、こういった行為が禁止されます。
これにより、発注者と受注者が対等に価格交渉を行い、適切な価格転嫁が進むことが期待されます。
2 手形払等の禁止(取適法5条1項2号)
改正前においては、下請代金の支払いにおける手形利用は一定の条件の下で認められていましたが、親事業者が下請事業者に資金繰りに係る負担を求める商慣習が問題視されていました。
そこで、改正により、下請代金の支払いに手形を使用することが全面的に禁止されます。また、その他の支払手段(電子記録債権やファクタリング等)についても、支払期日までに下請代金に相当する金銭(手数料等を含む満額)を得ることが困難なものは禁止されます。
手形等を用いて下請代金の支払いを行っている場合、速やかに対応を検討する必要があります。
3 運送委託の対象取引への追加(取適法2条5項、同条6項)
改正前においては、下請法の適用対象となる取引は、「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」の4つでした。
このうち、「役務提供委託」とは、他者から運送やビルメンテナンスなどの各種サービス(役務)の提供を請け負った事業者が、請け負った役務の提供の全部または一部を他の事業者に委託すること(再委託)をいいます。メーカーや卸売事業者等が、自社で製造した製品や自社で販売する商品を顧客に向けて運送する際、荷主として運送を運送事業者に委託することは、いわゆる自己利用役務に当たり、適用対象外とされていました。
しかし、立場の弱い物流事業者が、荷役や荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業者間の問題がありました。
そこで、改正により、事業者が、販売する物品、製造を請け負った物品、修理を請け負った物品又は作成を請け負った情報成果物が記載されるなどした物品について、その取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対して運送する場合に、その運送の行為を他の事業者に委託すること(=「特定運送委託」)が、下請法の対象取引として追加されます。
これにより、物流業界における適正取引が進み、立場の弱い事業者の保護の強化が期待できます。
4 法律名・用語の変更(取適法2条8項、同条9項)
従来使用されていた「下請」や「親事業者」という用語は、上下関係を連想させ、発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるといった批判がありました。また、時代の変化に伴い、発注者である大企業の側でも「下請」という用語は使われなくなっています。
そこで、改正により、以下の法律名・用語が変更されます。
「親事業者」→「委託事業者」
「下請事業者」→「中小受託事業者」
「下請代金」→「製造委託等代金」
「下請代金支払遅延等防止法」→「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」
新たな法律名の略称は「中小受託取引適正化法」、通称として「取適法」が想定されています。
これに伴い、旧名称を使用した社内規程やマニュアル類、帳票類の修正が求められます。
5 その他の改正事項
⑴ 製造委託の対象物(取適法2条1項)
改正前においては、メーカー等の物品の販売や製造を行っている事業者が、自社製品を製造するための型等の製造を他の事業者に委託する場合において、専ら物品等の製造に用いられる金型のみが製造委託の対象物とされており、木型、治具等については、製造委託の対象物とされていませんでした。
そこで、改正により、専ら物品等の製造に用いられる木型、治具等についても、金型と同様に製造委託の対象物として追加されます。
⑵ 発注内容等の明示義務(取適法4条)
口頭発注による様々なトラブルを未然に防止するため、親事業者は発注に当たり、発注内容(給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法)等を書面又は電子メールなどの電磁的方法により明示しなければなりません。
改正前においては、明示方法について、下請事業者から事前の承諾を得たときに限り、書面の交付に代えて、電磁的方法によることができるとされていました。
しかし、改正により、下請事業者の承諾がなくとも、電磁的方法によることができるようになります。
⑶ 遅延利息を支払う義務(取適法6条2項)
改正前においては、下請代金の支払遅延について、親事業者に対し、その下請代金を支払うよう勧告するとともに、遅延利息を支払うよう勧告することとされていましたが、減額については規定がありませんでした。
そこで、改正により、親事業者が、下請事業者に責任がないのに、発注時に決定した下請代金の額を減じた場合、起算日から実際に減じた額の支払いをするまでの期間について、減じた額に対して遅延利息を支払う義務が新たに追加されます。
⑷ 勧告規定の整備(取適法10条)
改正前においては、受領拒否等をした親事業者が勧告前に受領等をした場合や、支払遅延をした親事業者が勧告前に代金を支払った場合に、勧告ができるかどうかが規定上明確となっていませんでした。
そこで、改正により、既に違反行為が行われていない場合等の勧告に係る規定を整備し、勧告時点において委託事業者の行為が是正されていた場合においても、再発防止策などを勧告できるようにします。
終わりに
今回の改正により、発注者と受注者の関係がより対等なものとなり、取引環境の適正化が期待されます。特に価格転嫁の問題や手形払の禁止、運送委託の対象取引追加など、実務に直接的な影響を与える改正が多く含まれています。この改正法の施行により、下請事業者の立場が一層強化され、健全な取引環境が整備されることが期待されます。
(栗本真結)