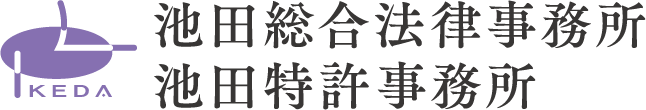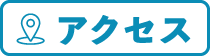情報流通プラットフォーム対処法について
1.はじめに
SNSの利用が増加し、多くの人にとって重要なコミュニケーションツールとなっています。その反面、インターネット上での誹謗中傷やプライバシーの侵害等、違法・有害な投稿も増加しており、深刻な問題となっています。
そこで、違法・有害な投稿への対応を強化するため、従来のプロバイダ責任制限法を改正した特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律、通称情報流通プラットフォーム対処法が、今年4月1日から施行されます。
情報流通プラットフォーム対処法では、新たに大規模プラットフォーム事業者に対し、①対応の迅速化、②運用状況の透明化に係る措置が義務付けられました。
これから2回に分けて、従来のプロバイダ責任制限法からの主な変更点について、ご紹介していきます。
本コラムでは、①対応の迅速化について、ご紹介します。続いて第2回目では、②運用状況の透明化等についてご紹介します。
なお、従来のプロバイダ責任制限法から変更のない部分については、2024年12月4日付法律コラム(リンク貼り付け)をご参照ください。
2.対応の迅速化について
総務省の委託事業として設置された違法・有害情報相談センターでは、インターネットの一般利用者などから、被害に関する相談を受け付けています。
ここに寄せられる相談は、年々増加していますが、中でも多いのが、住所・電話番号等の掲載(プライバシー侵害)、写真・映像などの掲載(肖像権侵害)、名誉毀損に当たる投稿、わいせつ画像等違法・有害情報の掲載です。
これらについて、被害者としては、まず事業者に情報の削除を求めたいと考えるのが一般的です。
そこで情報流通プラットフォーム対処法では、被害者からの削除の申請に対して、大規模なプラットフォーム事業者を対象に、一定の対応が義務付けられるようになりました。
ここで、大規模なプラットフォーム事業者とは、月間アクティブユーザー数が一定規模以上など、サービスの利用者数の多い事業者が想定されています。
大規模プラットフォーム事業者に義務付けられる対応は、以下の3点です。
①被害者から削除の申出を受けるための窓口や手続きを整備・公表すること
②削除の申出への対応体制を整備すること
③削除の申出に対する判断・通知を行うこと
上記①では、被害者がインターネット上で削除の申出をすることができ、且つ、申出の手続きが容易であることが求められています。
上記②では、事業者は、権利侵害への対処について十分な知識経験を有する者を選任することが求められています。
また、③削除の申出に対する判断・通知については、事業者は、被害者から削除の申請を受けてから、1週間程度で迅速に判断・通知を行わなければなりません。
従来のプロバイダ責任制限法では、事業者に対する上記対応は、定められていませんでした。
今後は、事業者は、表現の場を提供するだけでなく、不当な権利侵害に対して、より一層適切な対応をとることが求められます。
(石田美果)