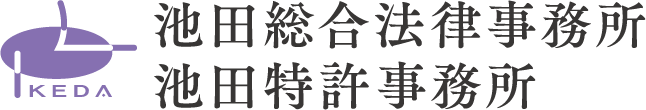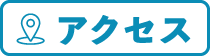相続手続の変更点について(戸籍の取り寄せ手続)
1 はじめに
相続の手続で最初にやるべき事は、相続人が誰か、また、遺産がどれだけあるかを調査によりはっきりさせることです。従前は、この調査にとても手間と時間がかかったのですが、昨今、制度の変更により調査の手間が大きく軽減されましたので、ご説明します。まず、今回の記事では、相続人調査の方法、具体的には戸籍の取り寄せの方法が大きく変わったことについて説明します。戸籍には、結婚や子どもの出生などの相続に必要な情報が記載されており、相続人の確定に必要不可欠な書類です。
2 従前の戸籍取り寄せの手続は大変でした。
この戸籍、従前の制度では、御本人の戸籍を取る場合においても、戸籍は本籍地でないと取り寄せられませんでした。そのため、本籍地と現住所が離れている場合には、本籍地の市町村の役場・役所まで出向くか、郵送で手続きをする必要がありました。
相続の場面でも同様で、父母・祖父母、戸籍を取る場合は、本籍地に出向いたり郵送したりで取り寄せなくてはならず、しかも本籍地を何度も変えていたりするとそのときどきの戸籍をたどって従前戸籍を取り寄せる事も必要で、その作業は膨大でした。
3 新たな広域交付制度での手続では、戸籍取り寄せの手間が大幅に省かれます。
令和6年3月1日から、改正戸籍法が施行されました。この法改正により新たに「戸籍証明書等の広域交付」を受けられることになりました。
広域交付制度を利用すると、遠方の戸籍についても、お近くの役所等で手続が可能となりました。遠方まで出向いたり、郵送の手続は不要になり、遠方が本籍地の戸籍の取り寄せがとても簡便になりました。しかも、度々本籍地を変えるなどして欲しい戸籍の本籍地が全国にあっても、1カ所の窓口で請求できます。相続の場面においても、父母祖父母の戸籍を一カ所の窓口で一括して請求できることになりました。
4 実際に戸籍を取得する手続を説明します。
広域交付制度を利用しての戸籍を取得するには、本人が窓口に出向き、運転免許証などの写真付きの本人確認書類を確認する必要があります。そのため、戸籍を集めることを弁護士などの代理人に依頼しても、広域交付で戸籍を集めることはできません。
また、取得できる戸籍は、ご本人だけのものではなく、配偶者や父母・祖父母、曾祖父母などの直系尊属、子・孫・ひ孫などの直系卑属も取得することができます。相続の場面で、例えば亡くなった親の出生から死亡までの戸籍を集めることができます。ただし、兄弟姉妹やおじやおば、甥や姪の戸籍の取得はできません。相続の場面において、常に相続人になりそうな親族の戸籍を取れる、と言うわけではありません。
5 おわりに
広域交付制度が始まったことにより、遠方の自治体からの出生から死亡までの戸籍の取り寄せは大幅に簡便になりました。
相続人の範囲がどこまでかは、離婚・再婚、養子縁組や認知の事実、また亡くなる順番によって大きく変わってくることがあります。また、集めた戸籍も、古いものだとなかなかこれらの事情を読み取りづらいこともあるでしょう。
相続手続については、相続人の確定以外にも、多くの検討要素があります。当事務所に、ぜひお気軽にご相談ください。
<山下陽平>