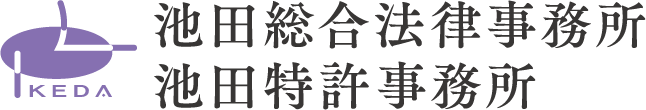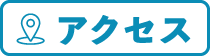第4回 民法の相隣関係の改正について
令和5年(2023年)4月1日から,いわゆる「所有者不明土地」関係に伴う民法改正の中で,相隣関係(そうりんかんけい)の民法の規定も改正され,既に施行されています。この相隣関係を含む民法物権編の大改正は明治時代以来です。
相隣関係は民法物権編・第209条~238条に定められています。
1 相隣関係とは
そもそも相隣関係とは,隣地,簡単に言えば「おとなり」との関係のことで,民法の相隣関係に関する規定は,おとなりさんとの関係を調整する規定です。
今回の改正では,「隣地使用権」「ライフラインの設備の設置・使用権」「越境した竹木の枝の切り取り」の各規定が見直しされています。
2 隣地使用権
(1)旧規定の問題点
改正前の民法では,「土地の所有者は,境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で,隣地の使用を請求することができる」(旧209条1項本文)と定められていました。
しかし,「隣地の使用を請求することができる」が具体的に何を指しているのかが明確ではなく,「障壁又は建物の築造・修繕」以外の目的で隣地を使用できるかどうかも不明確でした。
特に,隣地所有者が所在不明の場合などには,隣地使用権を使うことができないという問題があったため,所有者不明土地関係の法改正に伴って改正がなされています。
(2)改正法
そこで,改正法では次のとおりルールが明確化されました。
①隣地使用権の明確化
「土地の所有者は,次に掲げる目的のため必要な範囲内で,隣地を使用することができる。ただし,住家については,その居住者の承諾がなければ,立ち入ることはできない。
・境界又はその付近における障壁,建物その他の工作物の築造,収去又は修繕
・境界標の調査又は境界に関する測量
・越境した竹木の枝の切り取り」
と民法209条1項が改められました。
これにより,土地所有者は隣地について,上記の3つの目的のためであれば,隣地を使用する権利が明確に定められています。
ただし,権利として明確になっただけですので,例えば隣地に居住している隣地所有者が使用を拒否した場合には,裁判所に対して妨害排除の裁判等を提起して,判決に基づいて使用すべきことになります。
もっとも,法務省によれば,事案ごとの判断ではあるものの,隣地が空き地で,実際に使っている者もおらず,隣地使用を妨害する者がいない場合には,裁判を経なくても隣地を使用できるとの見解も示されています。
土地家屋調査士による確定測量では,隣地に立ち入って境界杭を確認し,測量をする必要がある場合がありますが,隣地所有者に対して測量のための立入りの権利があると明確に説明できるようになった点で,土地家屋調査士の業務が円滑に進みやすくなる法理論が増えたことになります。
②隣地所有者・隣地使用者(賃借人等)の利益への配慮
隣地使用権が明確になりましたが,隣地を使用する場合には,
・隣地使用の日時・場所・方法は,隣地所有者や隣地使用者のために損害が最も少ないものを選択しなければならない,とされています(民法209条2項)
・隣地使用をする場合には,
(原則)
あらかじめ,日時・場所・方法を隣地所有者(隣地所有者とは別に隣地使用者がいる場合には隣地使用者にも)通知をしなければならない(民法209条3項本文)
※『あらかじめ』は法務省によれば,通常は「2週間程度」前とされています。
(例外)
あらかじめ通知することが困難なときは,隣地使用を開始した後,遅滞なく通知する(民法209条3項但書)
【たとえば】
・隣地所有者が特定できない場合
・隣地所有者が所在不明である場合
⇒これらの場合,隣地所有者が特定されたり,所在が判明した後に遅滞なく通知すれば足ります。
3 ライフラインの設備の設置・使用権
(1)旧規定の問題点
電気の引き込み線,ガス管,水道管,電話線,インターネット用光ファイバーといったライフライン設備を引き込みたいが,そのためには隣地を通す(隣地を使用する)必要があっても,法律に明文がないため,とくに隣地所有者が所在不明である場合などには,ライフライン設備を引き込めないという問題が生じていました。
(2)改正法
①設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)の明確化
他の土地に設備を設置しなければ,電気,ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない土地の所有者は,必要な範囲で,他の土地に設備を設置する権利を有することが明文で定められました(民法213条の2第1項)。
②設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)の明確化
他人が所有する設備を使用しなければ,電気,ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を引き込むことができない土地所有者は,必要な範囲で,他人の所有する設備を使用する権利を有することも明文で定められました(民法213条の2第1項)。
③場所・方法の限定
ただし,設備の設置,使用の場所・方法は,他の土地や他人の設備のために損害が最も少ないものにする必要があります(民法213条の2第2項)。
④権利の実現方法
設備設置権・使用権がある場合でも,その設置や使用を拒否された場合には,裁判所に対し妨害禁止の裁判を提起し,判決に基づいて設置権や使用権を実現していくことが原則になります。
ただし,他の土地が空き家になっており,実際に使用している者がおらず,かつ,設備の設置や使用が妨害されるおそれもない場合には,裁判を経なくても適法に設備の設置や使用ができると,法務省は見解を示しています。
また,設備の設置工事などのために一時的に隣地を使用する場合には,上記の「隣地使用権」を活用することになります(民法213条の2第4,5項)。
⑤事前通知
他の土地に設備を設置し,または他人の設備を使用する土地の所有者は,あらかじめ,その目的,場所,方法を他の土地・設備の所有者に通知する必要があります(民法213条の2第3項)
・「あらかじめ」とは
通知の相手方が設備設置使用権の行使に対する準備をするのに足りる合理的な期間をおく必要があります。
法務省は,事案によるが,2週間~1か月程度としています。
・他の土地に設備を設置する場合には,他の土地に所有者とは別に使用者(賃借人等)がいるときは,使用者にも通知をする必要があります。
・通知の相手方が特定できない,所在不明といった場合でも,例外なく,通知が必要です(この点が隣地使用権と異なります)。
特定できない場合や所在不明の場合は,『公示による意思表示』(民法98条)を活用する必要があります。
⑥償金・費用負担の規律
ア 設置の場合
土地の所有者は,他の土地に設備を設置する際に
・設備設置工事のために一時的に他の土地を使用する場合は,実損害を償金とし て一括払いをする必要があり,
・設備の設置により土地が継続的に使用できなくなる場合には,設備設置部分の使用料相当額を償金として支払う(この場合は1年毎に定期払が可能)必要が
あります。
【土地が継続的に使用できなくなる場合とは】
例えば,水道管を地上に設置し,水道管の設置部分の土地が使用できなくなる場合などです。
したがって,水道管が地下に設置された場合は,地上の利用は制限がないことが通常ですので,償金の支払義務が無い場合もあります。
【償金以外に承諾料を支払わなければならないのか】
償金以外に設備を設置するに際して,承諾料を求められても,償金以外には支払義務がないので,承諾料の支払いを拒否することができます。
イ 使用の場合
・土地の所有者は,設備の使用開始の際に損害が生じた時は,償金を一括払いで支払う必要があります。
(たとえば)
水道管を接続する際に,一時的に断水したことに伴って生じた損害
・土地の所有者は,利益を受ける割合に応じて,設備の修繕・維持等の費用を負担する必要があります。
4 越境した竹木の枝の切り取り
(1)旧規定の問題点
もともと隣地から越境した竹木の『根』は,土地所有者が切り取ることができるとされていました。この点は,改正後も変更ありません。
これに対し,隣地から越境した竹木の「枝」を,土地所有者が切り取ることができるとする規定はなく,隣地の竹木所有者に枝を切るよう求める必要がありました。
もっとも,竹木所有者に枝の切除を求めても,竹木所有者が枝を切り取らない場合には,裁判所に訴訟を提起し,枝の切除を命じる判決を得て,強制執行する必要がありました。
しかし,植物である以上,枝は適宜剪定しない限り伸び続けるものですので,枝が越境するたびに訴えを提起しなければならないとするのは現実的ではありませんでした。
また,隣地の竹木が共有林の場合には,越境した枝を切るためには,竹木共有者全員の同意が必要と考えられており,特に財産的価値に乏しく放置されている共有林については,竹木共有者全員を探し出し,意思を確認して,全員の同意を得ることも現実的ではありませんでした。
(2)改正法
①越境された土地所有者による,越境した枝の切除する権利の明確化
越境された土地の所有者は,
・竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが,竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき
【相当期間】
法務省は「基本的に2週間程度」と考えられるとしています。
・竹木の所有者を特定できず,または竹木所有者が所在不明のとき
・急迫の事情があるとき
には,自ら越境した枝を切除することができる,とされました(民法233条3項)。
この場合の枝の切り取り費用は,竹木所有者が剪定費用を免れたと考えれば民法703条に基づき費用相当額を請求できると考えられています。
②竹木共有者各自による枝の切除
竹木が共有物である場合,各共有者が越境している枝を切り取ることができる,と定められました(民法233条2項)
③枝が越境している竹木の幹を切れるか
隣地に生えていて枝が越境している竹木の幹は,隣地所有者が所有する竹木そのものに手を加えることになりますので,今回の民法改正でも対象外です。
枝は毎年伸びるので,根本的に竹木を伐採してもらいたいと希望したとしても,幹から伐採することはできません。
5 相隣関係の弁護士の関与
相隣関係では,特に自宅を購入して,そこで長く住み続けている場合には,ご近所の目や今後住みづらくなるかもしれないという懸念もあります。
今回の相隣関係の改正の中でも,ライフラインの設備の設置・使用は,電気・水道・ガスという生活の根幹にかかわる事柄です。弁護士としてご依頼を受ければ,解決に向けての一助になることもできると思いますので,一度,池田総合法律事務所にご相談ください。
(小澤尚記(こざわなおき))