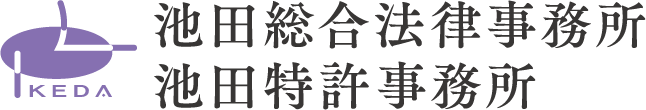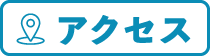大家さんが知っておきたい、賃貸経営トラブルへの対処法(連載・全6回)
はじめに
本ブログでは、今回から全6回にわたって、概ね以下のスケジュールで大家さん(賃貸人)向けの記事を連載します(あくまで予定であり、予告なく変更となる可能性がありますので、ご了承ください)。
第1回(今回) 令和4年4月15日 契約書作成の際の注意点
第2回 令和4年5月 1日 貸期間中のトラブルへの対応
第3回 令和4年5月15日 家賃の未払への対応(その1・家賃の回収)
第4回 令和4年6月 1日 家賃の未払への対応(その2・明渡請求)
第5回 令和4年6月15日 賃貸物件の取壊しのための立退き請求
第6回 令和4年7月 1日 賃借人(入居者)が死亡したときの対応
相続税対策といわれて賃貸アパートを建築したり、親から賃貸物件を引き継いだりして、賃貸経営に携わるようになったという方も少なくないと思います。
順調に賃料が支払われている間は良いですが、ひとたびトラブルが生じると、大家さんにかかる負担は小さくありません。
本コラムでは、よくある相談内容をもとに、弁護士の視点から発生しやすいトラブルについてご紹介をしますので、参考としていただければと思います。
第1回 契約書作成の際の注意点
Q 親の代から賃貸アパート経営をしていますが、管理会社を入れずに独自の契約書を使用しています。内容は非常に簡素なもので、これで足りるか心配なのですが、契約書にはどのような内容が入っている必要がありますか。
1 最低限必要な内容
賃借人との間で賃貸借契約書を取り交わすにあたって、契約書には最低限以下の記載が必要です。
・賃貸の対象に関する記載(例えば駐車場を含むか否かなど)
・賃料や敷金等の定め(途中で金額が変更されている場合には、別途賃料変更の合意書を作成するか、新たな賃貸借契約書を作成することが望ましいです)
・契約の当事者の署名・押印と契約締結の日付
これらの条項以外にも、契約書には、契約の期間、賃貸物件の取扱いに関する取り決め(用法遵守義務)に関する定め、契約の解除に関する定め等を入れるのが一般的ですが、以下では、特に問題となりやすい、原状回復義務、連帯保証人、更新のない賃貸借契約に関してご説明します。
2 原状回復義務について
賃貸アパートに入居中に、入居者(賃借人)があやまって壁などを傷つけた場合、大家さん(賃貸人)は、賃借人に対して、元に戻すように(修理に要する費用を負担するよう)に請求することができます(賃借人の原状回復義務といいます)。しかしながら、通常の使い方によって生じた損耗(通常損耗)や経年劣化による損耗(自然損耗)については、原則として賃借人には原状回復義務はありません。
もし、こうした通常損耗についても賃借人に原状回復を求めたい場合には、契約書において、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲を具体的に明記するなど、原状回復義務に関する規定を設けておく必要があります。
3 連帯保証人について
(1)契約書への記載内容について
ア 連帯保証を含む保証契約は、書面でしなければ効力が生じません(民法446条2項)。口約束で連帯保証契約を結んでも無効です。
したがって、連帯保証人を付ける場合には、契約書に連帯保証に関する規定を入れておく必要があります。
イ また、2020年4月以降に連帯保証契約を結ぶ場合には、連帯保証の極度額(上限)を契約書に記載しておかないと、連帯保証契約自体が無効になります。
独自の契約書を使用されている場合には、極度額の欄を追加しましょう。
(2)連帯保証人の署名・押印の方法
契約書には、連帯保証人にも署名・押印を求めることが一般的です。その際には、後から「そんな保証をした覚えはない」と言われないよう、自署をしてもらうと共に、実印による押印と印鑑証明書の提出を求めましょう。
(3)連帯保証人死亡への対応
連帯保証人が死亡した場合には、その相続人が連帯保証人の地位を引き継ぎます。しかしながら、2020年4月以降に連帯保証契約を結んだケースでは、賃貸借が続いている間に連帯保証人が死亡すると、原則としてその時点で発生していた未払分しか連帯保証人の相続人に請求できません。
このような事態が発生することを避けるためには、①連帯保証人を複数人にする、②連帯保証人が死亡した時には、直ちに別の連帯保証人を付けることを契約内容としておく、③家賃保証会社を利用する、といった手段が考えられますので、事前に検討しておきましょう。
4 更新のない賃貸借契約の締結
賃貸アパートの賃貸借契約書には、賃貸借の期間が記載されていることが多くあります。しかしながら、建物に関する通常の賃貸借契約では、入居者(賃借人)が契約の継続(更新)を望む際に、大家さん(賃貸人)から一方的に更新を拒絶することはなかなか認められません。
そこで、賃貸借契約期間の終了時に契約の更新をしないことを予め定めておくことができます(このような契約を「定期建物賃貸借契約」といいます)。
もっとも、この定期建物賃貸借契約を結ぶためには、あらかじめ、建物の賃借人に対し、当該契約には更新がなく期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、そのことを記載した書面を交付して説明しなければならないとされるなど一定の要件が定められています。要件を満たさない場合には、更新をしないという定め自体が無効となってしまいますので注意が必要です(借地借家法38条)。
5 まとめ
賃貸借契約においてトラブルが生じた場合には、まず、契約内容がどうなっていたかを契約書で確認することになります。事前に契約書で適切な定めをしておかなかったがために、思いもよらぬ負担を強いられることもあります。また、法改正や裁判所の新たな判断があった場合には、その改正等を踏まえて契約書を修正していく必要もあります。特に、独自の契約書を使用されている方は、定期的に専門家のチェックを受けることをお勧めします。
賃貸借契約書についてチェックをしてもらいたい、改訂をしたいとお考えの方は、ぜひ池田総合法律事務所にご相談ください。
(川瀬 裕久)