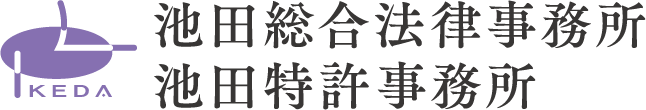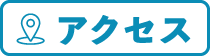定期金賠償(令和2年7月9日最高裁)について
事故に遭い、不幸にも将来にわたり後遺障害が残ってしまったとしたら、どのように損害金の支払いを一時払いで求めるのが良いのでしょうか。それとも定期的な支払いを求めるのが良いのでしょうか。本コラムでは、後者の定期金賠償について説明をします。
1 不法行為時の損害賠償の方法
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定めています。故意・過失によって他人の権利・利益を侵害する行為(=不法行為)をした人は、同条に基づき、損害を賠償する義務を負います。
賠償という言葉は、辞書的には「他の人に与えた損害をつぐなうこと」を意味しますが、法律的には、原則として、生じた全ての損害を金銭評価して、その合計額を支払うことにより賠償することになります(金銭賠償の原則:民法722条1項・417条)。
そして、実務上、多くの場合に損害賠償金は一時金として支払われます。
2 定期金賠償について
もっとも、事故により後遺障害を負った場合のように、損害が将来にわたって継続することが想定される場合には、一時金による支払いよりも定期的に一定額を支払う定期金賠償の方が適切な場合もあります。
法律上、損害賠償金の支払い方法は一時払いで無ければいけないという規定は存在しません。むしろ、1996(平成8)年に新設された民事訴訟法117条は以下のように定めています。
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第117条 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
この条文は、定期金賠償による判決が出た場合に、後遺障害の程度や賃金水準等が大きく変わった場合には、判決の変更を求める訴訟を提起することができることを定めたもので、定期金賠償が可能であることを前提としています。
また、実務上、定期金賠償によることも少ないながらあります。
3 最高裁判例の紹介
そんな中、交通事故で後遺障害が残ったケースで、その逸失利益について定期金による賠償を認めた判決(以下「本判決」と言います。)が、2020(令和2)年7月9日に最高裁で出されました(最高裁ホームページ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89571 )。
本判決は、事故当時4歳の子が道路横断中に大型貨物自動車に衝突され、脳挫傷、びまん性軸索損傷等の傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害が残り、労働能力を全部喪失した(全く働くことができなくなった)という事案です。被害者側は、上記後遺障害による逸失利益(得ることが出来なくなった利益)として、本来であれば働くことができた18歳から67歳までに取得できたはずの収入額を、各月払いの定期金によって支払うことを求めました。
これに対して、最高裁は、「交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において」、不法行為に基づく損害賠償制度の「被害者が被った不利益を補填して、不法行為がなかったときの状態に回復させる」という目的や「損害の公平な分担を図る」という「理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となるものと解される」とした上で、本件後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を対象とすることを認めました。
4 被害者側からみた定期金賠償のメリット・デメリット
被害者側からみたときに、定期金賠償は、実態に即した賠償を受けることができるというメリットがあります。
例えば、一時金による賠償を受ける場合、中間利息控除(※)がされた金額を受け取ることになりますが、その際の利率(現在は3%)で運用することは、実際のところは容易ではありません。金利がほぼ0に近い現在の状況であればなおさらです。しかしながら、定期金賠償であれば本来の金額を受け取ることができます。
一時金払いの場合、最初に多額の現金が入るため、つい使ってしまい、後々困るということもあります。特に、未成年者や後遺障害により自身でお金を管理することが困難な場合、親や親族などのお金の管理者が使ってしまうという危険性もあります。
さらに、先に紹介した民事訴訟法117条により、障害の程度が大きく変わったり、大幅なインフレが生じた場合に、定期金の金額を変更する判決を求めることも可能です(もちろん必ず認められる訳ではありませんが)。
他方で、定期金における一番のデメリットは、支払義務者が消滅したり、支払能力がなくなったりした場合に、定期金を支払ってもらえなくなる可能性があることです。交通事故等の実質的に保険会社が支払うというケースでは、支払われなくなる可能性は小さいですが、ゼロではありません。
また、後遺障害の程度が当初の想定より大幅に改善した場合や著しいデフレがあった場合には、民事訴訟法117条により、先ほどとは逆に定期金金額が下がる可能性もあります。もっとも、損害賠償が被害者が被った不利益の補填であることからすれば、不利益の程度が軽くなっているのであれば、減額されるのはやむを得ないものともいえます。
5 加害者側からみた定期金賠償のメリット・デメリット
後遺障害の程度等、損害額算定の基礎となる事情が大きく変わった場合に、民事訴訟法117条により定期金の金額を変更できる可能性があるということは、加害者側から見てもメリットになると言えます。
ただし、後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償が命じられた場合に、その後就労可能期間の終期より前に被害者が死亡したときに、民事訴訟法117条によって死亡後の定期金賠償の支払いを免除されるかというと、必ずしもそういうわけではありません。本判決を言い渡した裁判官の一人である小池裕裁判官は、補足意見として、上記のような場合には「被害者の死亡によってその後の期間について後遺障害等の変動可能性がなくなったこと」を理由として、「就労可能期間の終期までの期間に係る定期金による賠償について、判決の変更を求める訴えの提起時における現在価値に引き直した一時金による賠償に変更する訴えを提起するという方法も検討に値する」と述べており、死亡後の定期金賠償の免除では無く、一時金に変更しうるという見解を述べています。
また、加害者が任意保険等に加入していない場合には、定期金賠償=分割払いであることもメリットとして挙げられるかもしれません。
他方で、デメリットとしては、長期間にわたり支払いをしなければならないという債権管理上の負担がまずあります。
また、後の事情変更により、不利にもなり得ることはデメリットとも考えられますが、既に述べた損害賠償制度の目的・理念からすれば、やむを得ないことと言えるでしょう。
6 最後に
本判決により、交通事故や医療事故などで定期金賠償となるケースも増えるかもしれません。一時金と定期金、いずれの賠償を求めるべきか検討する必要も生じるものと思われます。
交通事故、医療事故等による損害賠償の請求を検討される際には、ぜひ池田総合法律事務所にご相談ください。
※中間利息控除については、本コラム 2020(令和2)年4月2日「民法改正による交通事故の損害賠償請求の影響は?」3の(2)をご覧ください。
(川瀬 裕久)