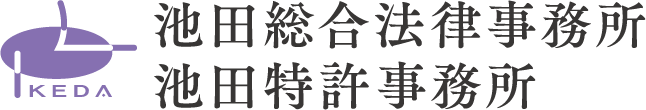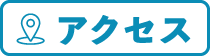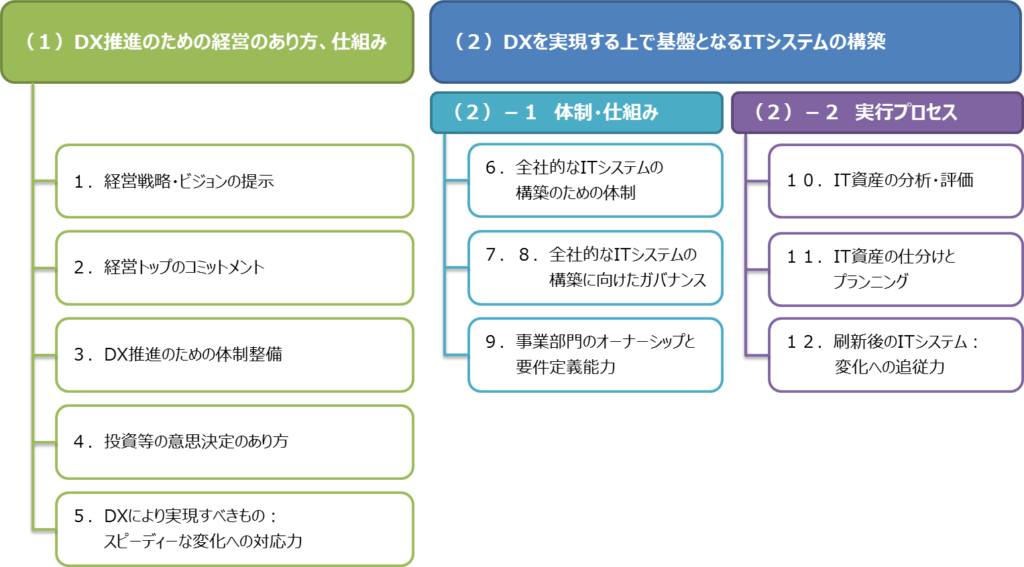スタートアップの資金調達について
1 VB(Venture Business)、「ベンチャー企業」は和製英語で、英語では”startup company”, “startup”と呼ばれ、どちらかというと、最近では日本でも「スタートアップ」という言葉が主にIT業界を中心に使用されるようになっており、その差は明確にされないことが多いように思われます。ベンチャーは新規の起業が想起されることが多いのですが、起業だけでなく既存の大企業が新たな取り組みに挑戦することもその範疇に入ります。
新たな市場分野の開拓、新規の雇用の創出、新たな技術やビジネスモデル(イノベーション)の創出、特に、ビジネスモデル(イノベーション)の創出に関しては、規制や業界の常識を覆すことが必要であり、企画力・実行力が重要になってきています。
2 新型コロナウィルス禍で難しさが増したという声もありますが、2020年4月から12月の会社設立件数は前年比で微減でした。スタートアップの1つの目標であるIPO(新規株式公開)市場は結構活況を呈しており、20年のIPOは、3月4月には延期した企業もありましたが、19年を上回っています。
スタートアップ時の資金調達方法として、まず考えられるのは、大別して、
① 自社の既存資産を基に資金調達する「アセット・ファイナンス」・・・土地や建物が生み出すキャッシュフローや、売掛債権などを裏付けに資金調達する手法
② 銀行借入や債券発行による「デット・ファイナンス」・・・一定の金利を支払い、返済期日まで資金を借り入れる方法
③ 株式の発行による「エクイティ・ファイナンス」・・・株式を発行して資本の調達を行う方法
その他、最近では
④ クラウドファンディングー自らのアイデアをネット上でプレゼンテーションして賛同者を募り資金援助を得る方法
⑤ 補助金や助成金の活用―地域の貢献や雇用創出などを要件として、中小企業対象の操業助成金や非正規雇用労働者を正社員化した場合のキャリアアップの促進助成金など。年度ごとに制度が変更されること多いと思われますので、要件に注意。
があります。
資産の乏しいスタート時に①は難しく、②は差し入れる十分な担保がある場合や事業のキャッシュフローの蓋然性が高い場合に可能であり、信用力の高まった上場ベンチャーではよく活用されています。③の株式発行は、デット・ファイナンスのように返済義務がない分、資金の出し手である投資家の期待するリターンは高くなります。
3 上場企業となれば、③のエクイティ・ファイナンスは、大きく「公募増資」「第三者割当増資」「新株予約権による資金調達」の3つに分類することができます。
ア公募増資は、上場企業が証券会社を通じて行う資金調達です。特徴は証券会社が株を引き受けてくれるとすぐに資金の調達が実現する点です。国内の公募増資では合理的な事業計画に基づく厳格な資金使途の設定が求められることや、将来のM&A資金を今確保しておきたいというニーズには活用が難しいという点に留意する必要があります。
イ特定の第三者に株式を割り当てる第三者割当増資は、割り当て可能な第三者というのはそう簡単には見つかりませんし、割当先からはどのようなシナジーが見込めるのかや今後の経営権をどうするかなど、さまざまなポイントを検討する必要があります。
ウ近年よく使われる新株予約権による資金調達は、第三者に新株予約権の割り当てを行い、割り当てを受けた第三者が新株予約権を直前の株価に基づいた行使価格で行使することで上場企業が資金を調達する手法です。この手法の特徴は、公募増資や第三者割当増資とは違い、資金調達が一定期間を通じて行われる点です。上場ベンチャーにとっては資金調達が一度で完了しないデメリットがある一方、株価に連動する形で調達額も変動するため、将来成長を見込んでいる企業にとっては、株価が上昇する局面であれば、同じ株数であってもより大きな資金調達が可能になるというメリットがあります。調達のタイミングは慎重に行う必要があります。
4 非公開会社新株発行における新株発行の手続きの概要について、整理しておきたいと思います。
募集事項の決定には株主総会の特別決議が必要で、総会の1週間前までに株主に対して招集通知を送付しますが(ただし、全員の同意があれば、招集手続は不要)、非公開会社では取締役に委任することが可能で、株主総会決議から1年以内に払込期限を設定します(会社法200条)。
ベンチャー企業が株式を用いて第三者から資金調達をする場合、実際には新株発行を行うことを決定する時点で、誰が何株を引き受けるかが決まっていることが通常です。簡略化された、募集事項及び割当先の決定→出資の履行→変更登記といった手続で進めることが可能です。総数引き受け契約を締結する場合には、株主総会の決議を省略(または株主総会の特別決議に基づく取締役会決議)を行い、同日払い込みを行えば、1日で新株を発行することも可能です(会社法205条など)。
このような場合、引受人と会社の間で、募集株式の総数引受契約書を交わしておきます。
また、経営への関与を行うのかなどについて、バリエーションを付けるため、種類株式を発行することも考えられます。
なお、株式など有価証券の募集については、金融商品取引法の規制を意識する必要があります。もっとも、①特定の投資家のみを相手方とする特定投資家私募や、②適格機関投資家のみを相手にする場合(プロ私募)、③50名未満の者を相手方とする少人数私募は例外として定められていますので、ベンチャー企業の場合、③の例外を利用して金商法の開示規制を受けないこととする場合が多いものと思われます。
副業としてスタートアップ起業すること、会社の別部門としての立ち上げなど、いろいろなスタートがあると思います。業種や規模に応じてということになりますから、ご相談ください。
<池田桂子>