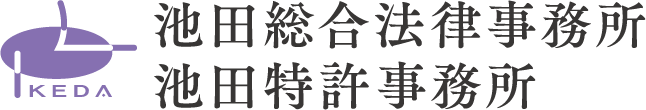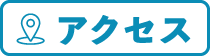相続人がいないときの財産の遺し方
1 相続人がいない場合の相続財産の行き先
2025年12月17日のコラム「増えている相続財産清算人制度の利用」でもご紹介しましたとおり、亡くなった方に相続人がいない場合(法定相続人全員が相続放棄をした場合を含む)には、亡くなった方の相続財産(遺産)は、相続財産清算人が管理し、最終的には国庫に帰属することとなります。
2 生前に相続財産の譲渡先等を決めておく方法
「法定相続人はいないが、ある程度の相続財産があるので、国庫帰属となるよりは生前にお世話になった人に渡したい」という場合、2026年1月15日のコラム「相続財産清算人制度(特別縁故者に対する相続財産分与)相続財産清算人制度(特別縁故者に対する相続財産分与)」でご紹介した方法により、生前に世話をした人が特別縁故者に当たるとして、相続財産の全部又は一部がその人に渡る可能性もあります。しかしながら、この方法は、特別縁故者が申立てをする必要がありますし、最終的に分与を受けられるか否かは、裁判所が決めるため、確実に渡せるわけではありません。
そこで、相続人ではない誰かに確実に相続財産の全部又は一部を渡したいと考えた場合には、事前に遺言書を作成したり、民事信託契約を締結したりするなどして、準備をしておくことが望ましいです。
具体的には、例えば以下の様なケースが考えられます。
<想定されるケースの例>
①婚姻関係の無い同居人やパートナーに相続財産を渡したい。
②生前飼っていたペットの世話をしてもらいたい。
③理念に共感できる団体に寄付をして活動に役立ててもらいたい。
3 遺言による準備の例
⑴ 遺言とは
ある人の最終意思が一定の方式で表示されたもので、例えば、その人が所有している自宅や預貯金を誰に承継させたいか等を記載したものです。
遺言書には自ら作成する自筆証書遺言と公証役場で作成してもらう公正証書遺言があり、自筆証書遺言については法務局で保管することができます(2024年12月15日コラム「遺言書保管制度のその後 」参照)。
⑵ 利用例と注意点
ア 2のケース①
同居人やパートナーである「Aさんに、全財産を遺贈する」などと記載することにより、Aさんに相続財産を渡すことができます。なお、このような書き方にすると、Aさんにプラスの財産(不動産、預貯金等)だけでなくマイナスの財産(借金、連帯保証債務等)も引き継がれるため注意が必要です。
イ 2のケース②
例えば、生前のペット仲間で世話をしてもらえそうなBさんに相続財産を全て渡す代わりに、ペットの世話をすることを条件とする遺言を作成することが考えられます(このような渡し方を「負担付遺贈」と言います)。
負担付遺贈を受けた人がその負担した義務を履行しない場合には、相続人が家庭裁判所に遺言の取消しを求めることができますが(民法1027条)、このケースのように、相続人がおらず、かつ、世話の対象がペットである場合には、実際のところ、Bさんが本当にペットの世話という義務を履行しているかをチェックすることは難しい点に注意が必要です。
また、このような内容の場合には、いきなり遺言書に書くのではなく、事前にBさんとよく話をして、具体的に世話の仕方などを取り決めた上でお願いしておくべきでしょう。
ウ 2のケース③
遺言に、寄付する先を記載しておくことになります。日本赤十字社のようにウェブ上で寄付について記載している団体もありますし、生前に身の回りの世話をしてもらった法人等に寄付をすることもあり得るでしょう。
寄付をしたいと考える場合には、事前に、寄付先の団体に、寄付の方法等を相談しておくと良いと思います。
エ 遺言執行者の指定
せっかく遺言書を作成しても、それが実現されなければ意味がありません。遺言書には必ず遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定しておきましょう。
4 民事信託による準備の例
⑴ 民事信託とは
民事信託とは、ある信頼できる人(受託者)に対して、土地や金銭などの財産(信託財産)を移転し、ある人(受益者)のためにその財産を管理・処分等をしてもらう制度のことを言います。
民事信託は、依頼をする人(委託者)と受託者との契約で設定することができるほか、遺言によって設定することも可能です。
⑵ 利用例と注意点
ア 2のケース①
前述のとおり、遺言書で同居人やパートナーであるAさんに相続財産を渡すことは可能ですが、Aさんが高齢であったりして財産管理が難しいような場合には、信頼できるCさんに不動産や金銭等を渡し、毎月少しずつ生活費相当額をAさんに渡したり、Aさんの代わりに不動産を管理したりしてもらうような信託をすることが考えられます。
イ 2のケース②
遺言書でペット仲間のBさんに一度に財産を渡してしまうと、その後、ちゃんとペットの世話をしてもらえるか分からないため、信頼できるCさんに金銭等を渡し、毎月少しずつBさんに渡してもらうような信託をすることが考えられます。
ウ 2のケース③
この場合は、基本的には遺言による対応で特に問題は無いと思いますが、渡すタイミングや渡し方等で何か細かく決めておきたいことがある場合には、信託による方法も選択肢に入るかもしれません。
エ 受託者や信託を監督する者の指定
信託を設定するあたり、最も悩ましいのが受託者を誰にするかです。基本的には信頼ができる誰かにお願いをすることになりますが、そのような人が見つからず信託を断念するケースも少なくありません。
また、信託を設定する際に、受託者の財産管理状況を監督する人(信託監督人や受益者代理人)を指定しておくことが望ましいと思います。
5 まとめ
今回は、相続人がいない場合に、相続財産がそのまま国庫に帰属してしまわないよう、生前にできる対策についてご説明しました(なお、これらの対策は、相続人がいる場合にも利用可能です)。
こうした制度を活用し、お世話になった人やのこされるペットのために相続財産を使いたいとお考えの方は、池田総合法律事務所にご相談ください。
(川瀬 裕久)